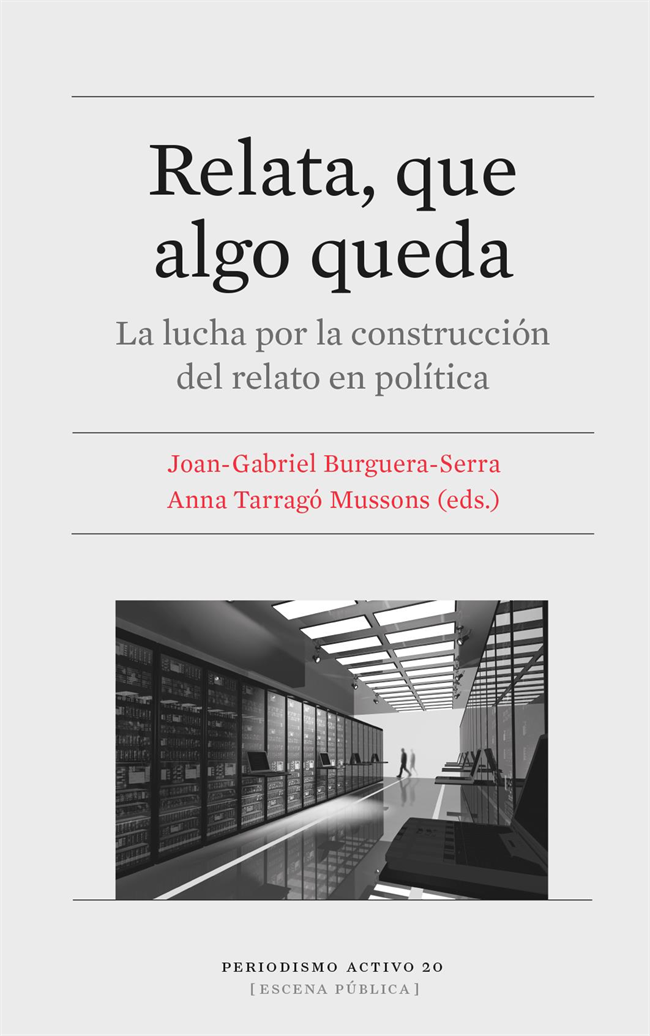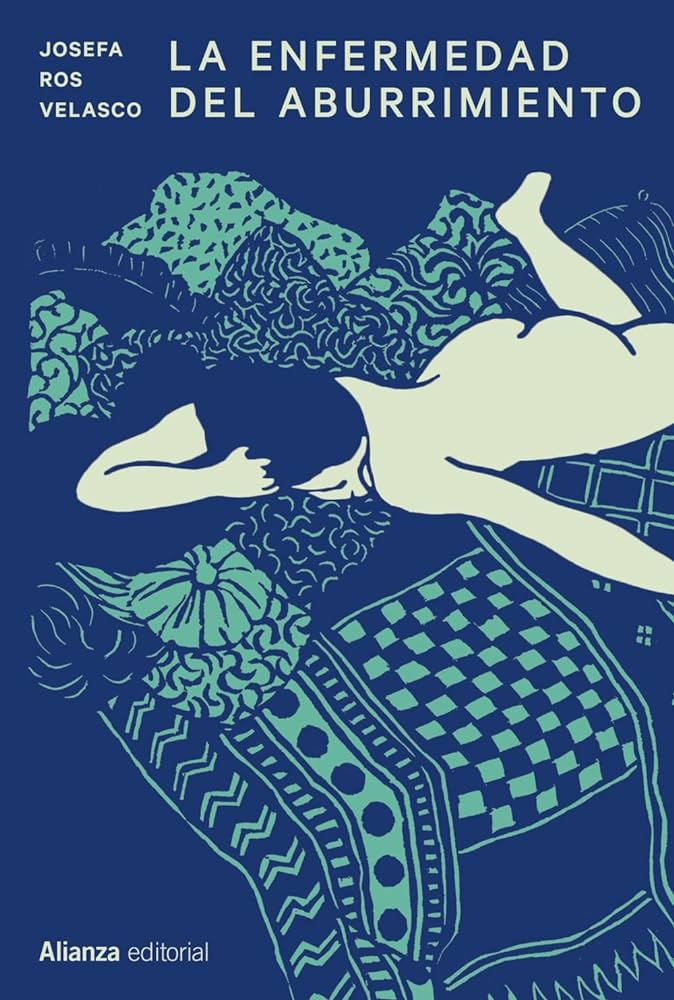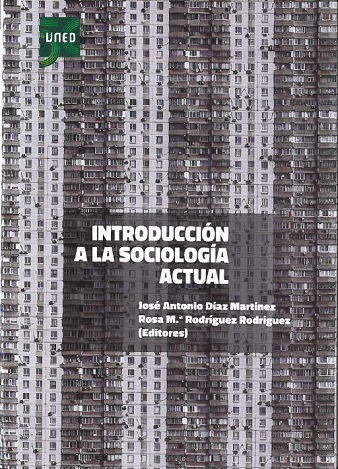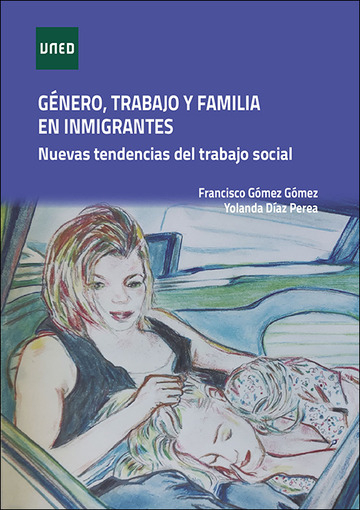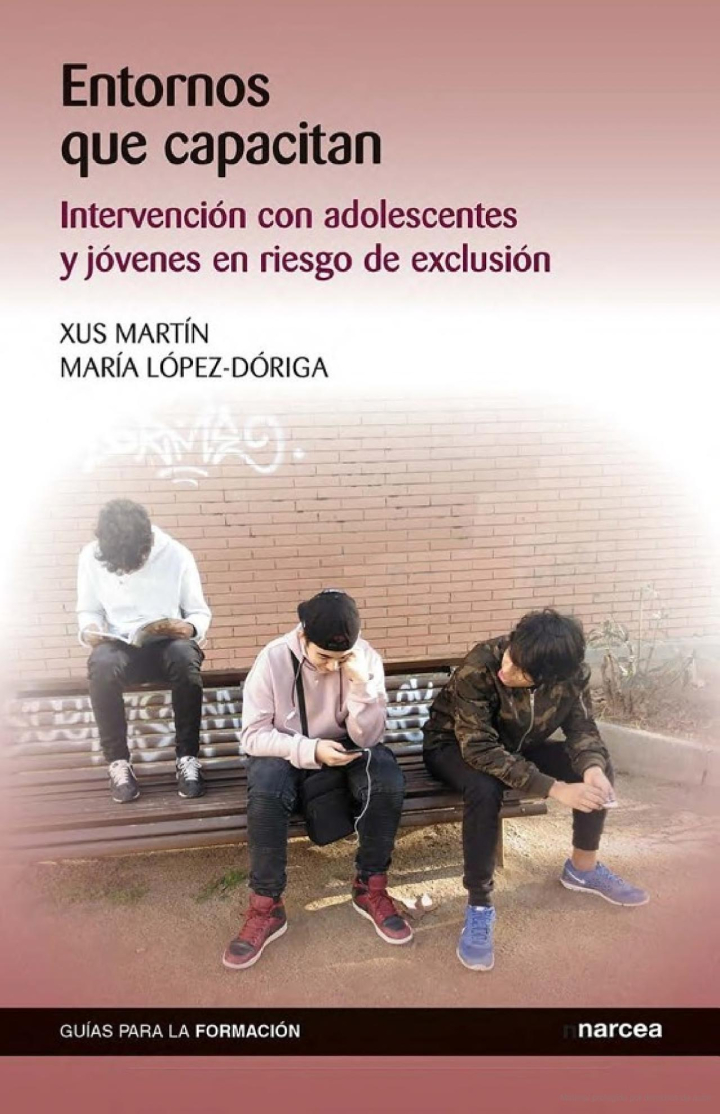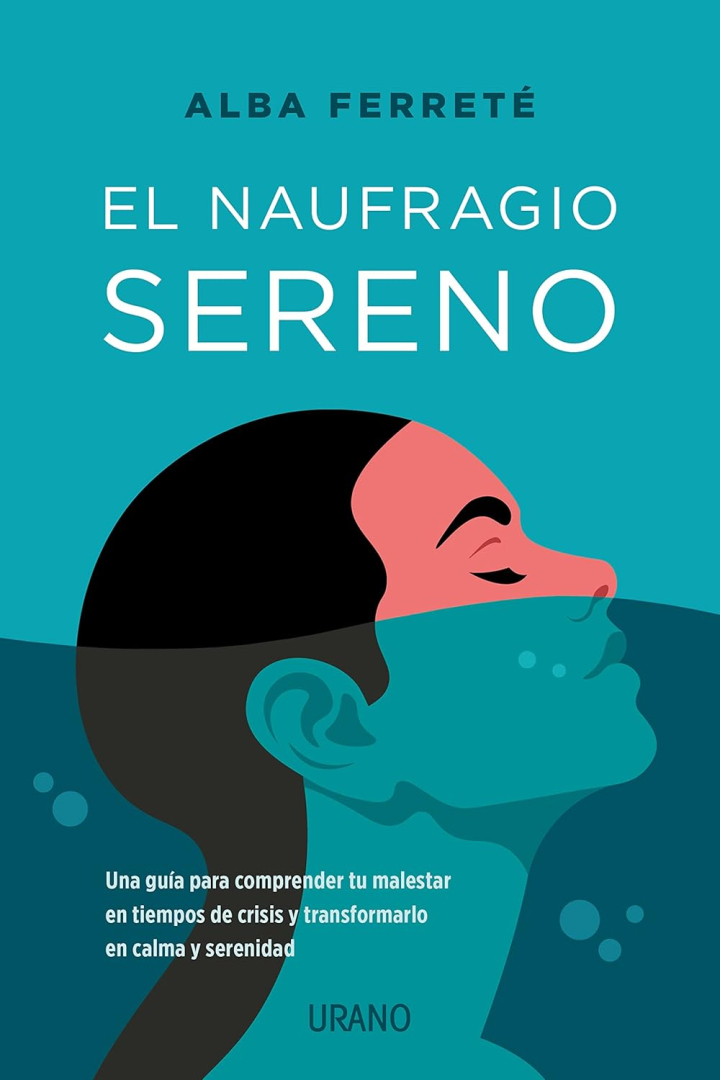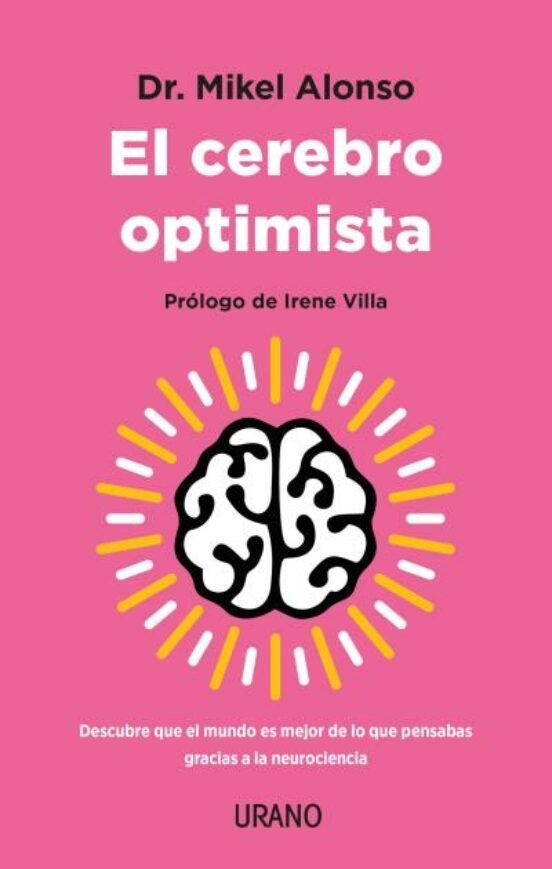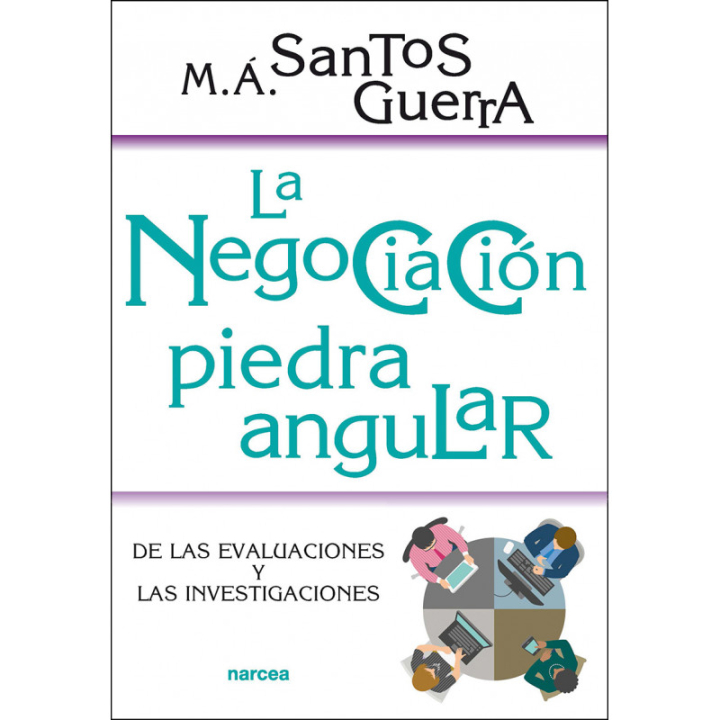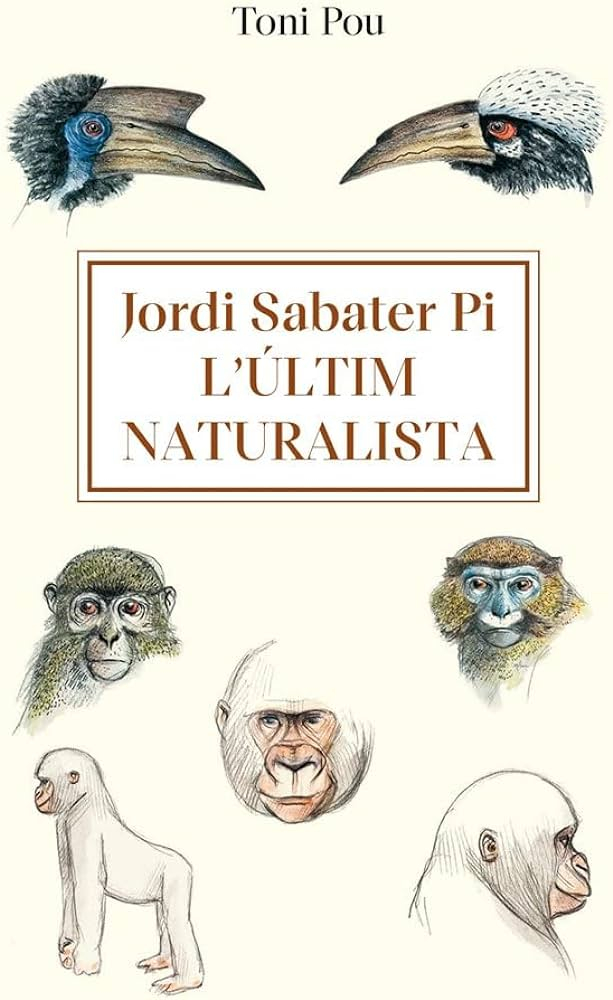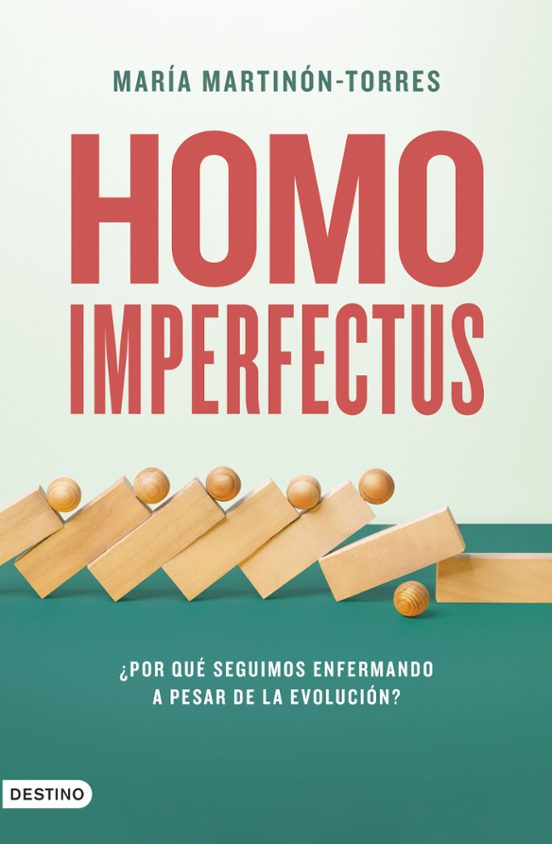スペイン新刊書籍
バウマンが予期した「液状化する社会」は、公共の言説や、あらゆるフォーマットの画面上に留まらず、SNSの中にも無限に表れている。これらのコンテンツは必ず〝ストーリー〟を必要としている。そこから発せられるメッセージはそれ自体が目的となり、装飾や誇張があったり、明らかに推測に基づいているものであっても、ほぼ問題視されない。重要なのは、それが相応な構造を有し、狙っている戦略に合致しているという点である。
退屈というのは、現実が期待に応えられないときに生じてわれわれを悩ます日常的な現象だ。それは、ごく浅い一過性のこともあれば、深く永続的の場合もあり、われわれ誰もが時折経験する。退屈は集団でも感じることがある。人類はその苦痛から逃れるため、あらゆることを試してきた。それは人間としての創造性を生み出させる一方、最悪の怪物も誕生させる。その苦しみは病的であり、病気とさえみなされることがある。しかし、退屈は単なる症状でしかない。
社会学の入門書。冒頭において、社会学の視点が一般常識とは異なる点を指摘し、社会科学の方法論を用いて、なぜ物事がそのようになるのかを説明している。つまり、社会学は社会の現実やある社会現象がどのようなものかを書き記すだけでなく、社会的な出来事や現象に対する説明を見出そうとするものなのだ。社会学はその始まり以来、社会の現実を客観的に研究し、社会生活の規則性や法則を発見するという科学的な意図を有してきた。
移民という現象にジェンダーの視点から統合的アプローチを行った作品。大きな不均衡が存在するこの世界の人間開発を巡る女性と移民が果たす役割を、移民受け入れ社会という背景におけるその優れた社会的機能について示しつつ論じている。本書において、フィールドワークは、現象に対する過度なエスノセントリズム的な解釈を避けるために、現実から切り取られた側面を示し、かつ、当事者にとっての移民の意味をより深く理解できるよう提示される。
早い段階で学業を放棄した青少年の教育は、彼らの学習能力のなさや社会的無能さを強調するような意見をあれこれと生みがちだ。だが、それは実際にはもっと複雑な現実を覆い隠してしまう性急な判断と言える。本書の中で著者は、排除されるおそれのある若者が、学習能力やコミュニティでの生活能力の点で劣っているわけではないという事実から出発し、環境が人間の統合的な発達に与える影響に着目していく。
人生の危機は、うまく導くことですばらしいものとない得る。現実の挫折に伴う精神的な苦痛や空虚さの下には、自らの内面を見つめ、内なる革命を実行する可能性が秘められているのだ。失われた何かが人間関係であれ、仕事であれ、物質的なものであれ、あるいは長いこと抱き続けた夢であれ、違いはない。われわれは、失うことは永遠の罰ではないとわかっているので、被害者意識、感情的依存、考えすぎといった状態から、信頼感、平穏、心の中の自由へと気持ちを移行させることが可能だ。
脳は無数の複雑なタスクをこなし、信じがたいほどの働きをするすばらしい器官だ。だが、われわれを幸福にするようには設計されていない。進化というものは、われわれを生存させるためのものであり、幸福に導くようには仕組まれてないのだ。幸い、人間の脳は主な特徴のひとつとして可塑性を有しており、今日、われわれは生物として何百万年もの進化を経た結果、脳の構造を新たな現実に適応させ、神経学的なメカニズムを利用して自分なりの幸福を構築するのに必要な知識を獲得した。
本書は筆者の持つふたつの源泉から生み出された。いずれも同様に重要なもので、ひとつは読書、熟考、同僚との議論。もうひとつは、半世紀近くにわたる多くの調査や評価から培われた経験だ。ネゴシエーションは、調査および評価の中で生じるものである。ここでこのふたつの課程を区別したのは、全ての評価が調査の結果として出てくるものあったとしても、全ての調査が評価に辿り着くというわけではないからだ。探求の形態にはそれぞれ特殊性があり、求められるものは異なる。
サバテル・ピの物語はまるで小説のようだ。しかし事実である。17歳でアフリカに渡り、30年後にバルセロナに戻ってきた彼は、学位すら有していなかったが、世界で最も有名な霊長類学者のひとりとなった。サバテルは、学問の世界を超え、学界に普及していた人類の概念を書き替えてしまうほどの貢献をした。彼の経歴は、好奇心と粘り強さ、そして自然に対する敬意に満ちている。また、自らをフンボルトやダーウィンの後継者であると公言していたが、彼らと同じような科学的探求へのロマンに満ちていた。
マリア・マルティノン=トレスは、本書を通じ読者を生物学の漆黒の闇の片隅にまで誘い込み、われわれが不完全であるというレッテルを貼ってしまったことで、ホモ・サピエンスの優れた適応力の重要な側面が隠されてきたことを明らかにする。進化論に照らし合わせると、ガン、感染症、免疫系障害、不安、心血管事故、神経変性疾患、老化、死に対する恐怖といった人間の大きな病は、変化する世の中で生き残ろうとする人類という種の闘いの変遷を物語るものだというのだ。