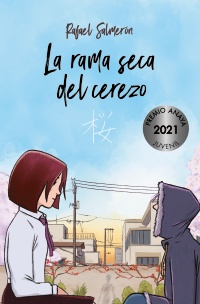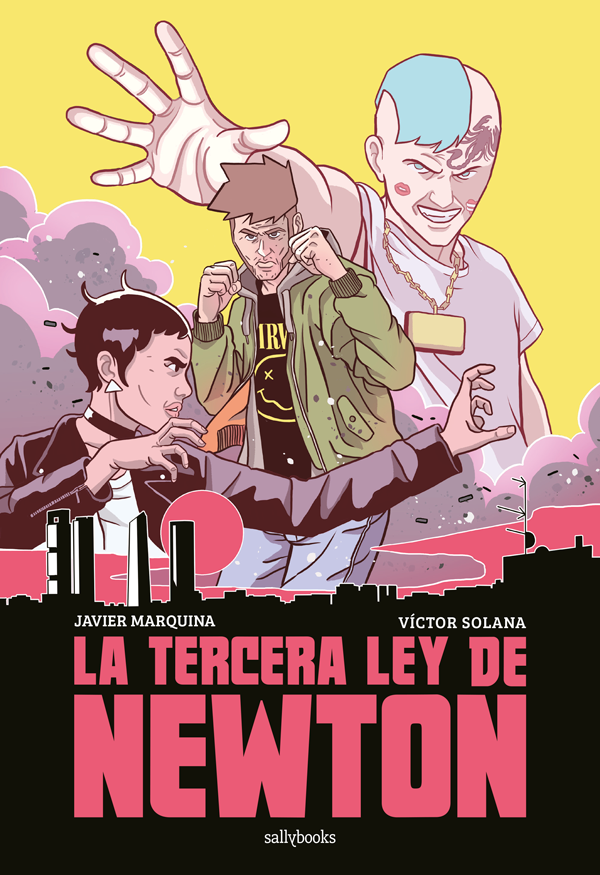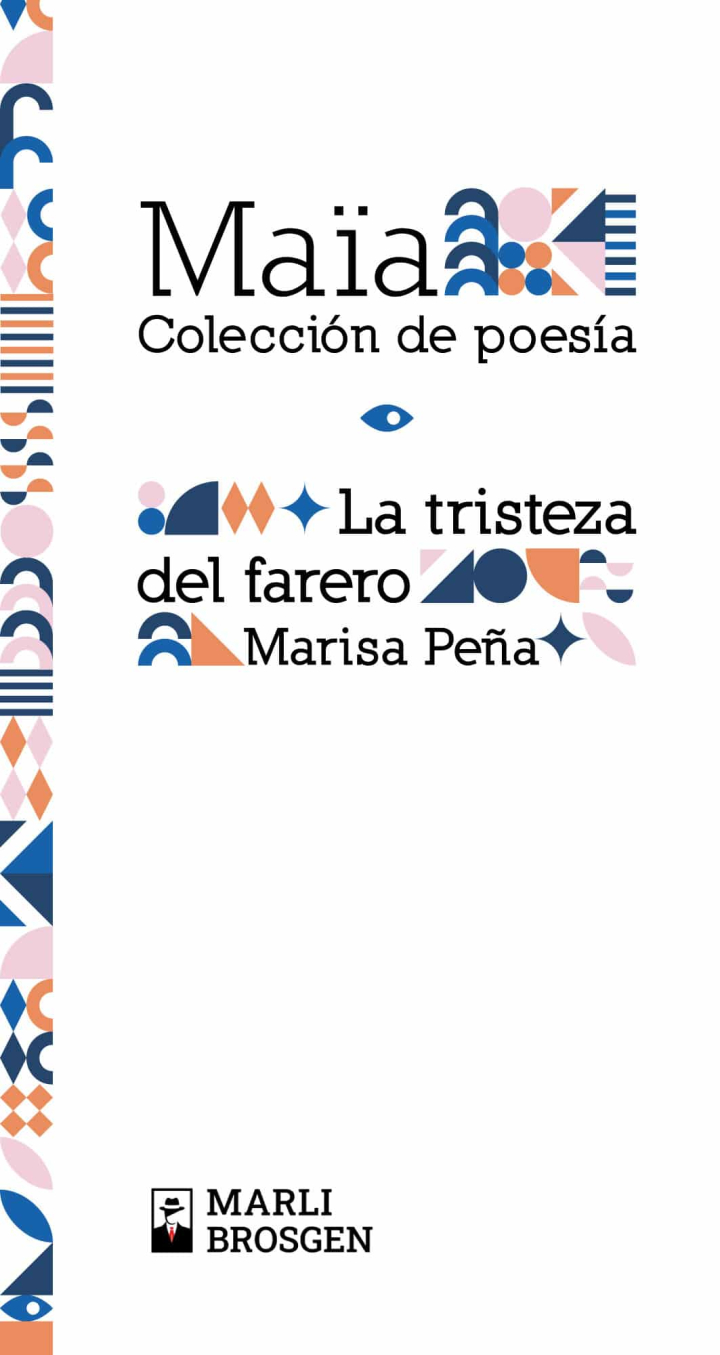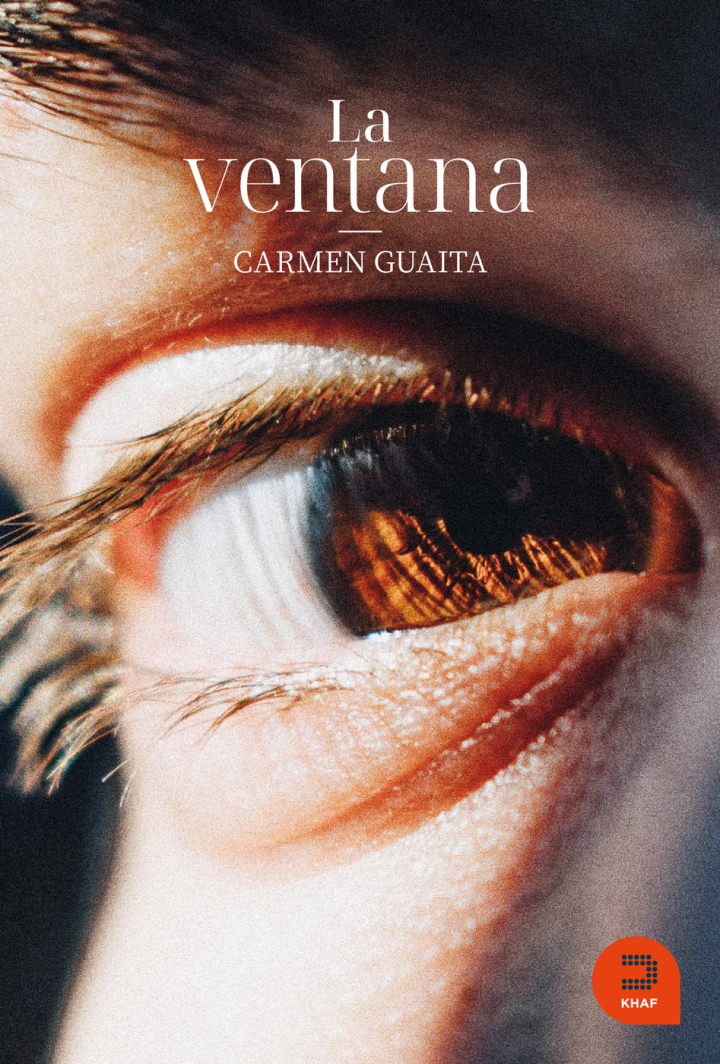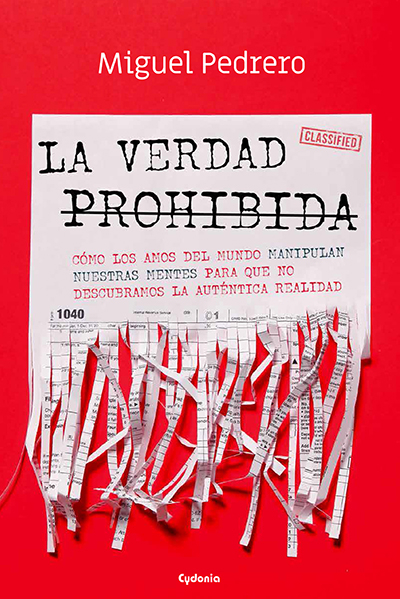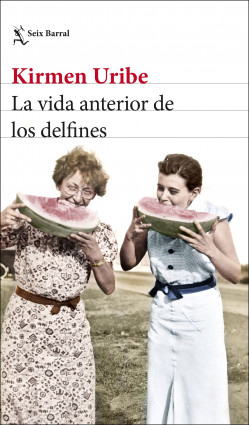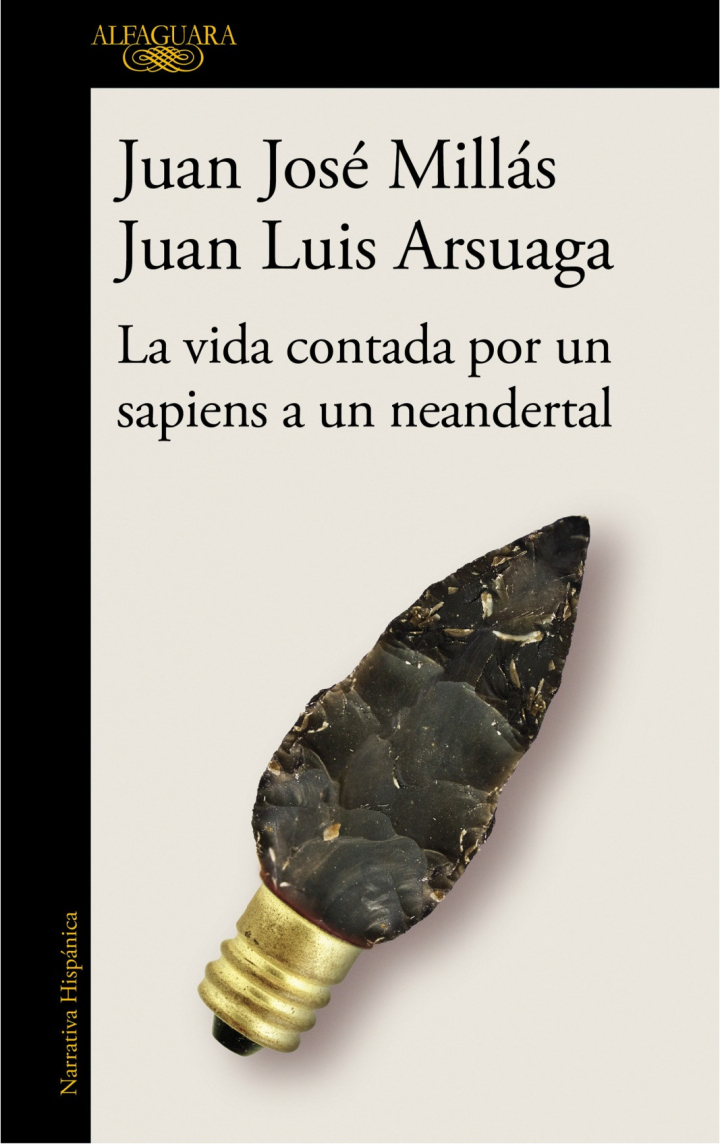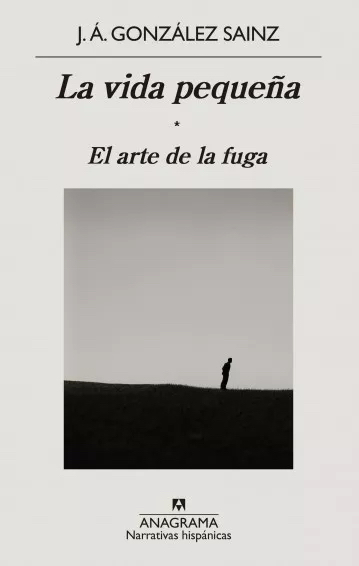スペイン新刊書籍
友情と克服を描く感動的な物語。1945年、原爆が落ちる直前の広島の街で、イチローとマスジは遊んでいた。現代の広島で、手の不自由な10代の少女サクラは、クラスメートの嘲笑と家族間での孤立をどうにかやり過ごしている。母には愛されていないと思い、仕事に没頭する父とはほとんど顔を合わせない。ネット上の友だちのアイコは別の街に住んでいて、実際に会うのは難しい。彼女の夢は漫画家になることだが、それは叶わないことだとわかっている。
エネアスは地球にただひとりのスーパーマン。だが、そのことに疲れてきっており、恋人のベリットとパーティー三昧の日々を送っていた。地球を太陽に打ち上げることもできるのに、ぐったりしながらドラッグをやっている方が性に合ってると思っているのだ。一方、ベリットはエネアスに夢中でありながら、パーティーで知り合ったバカっぽい若者が自分に言い寄ってきても好きにさせていた。何もかも普通に見えるが、ちょっとしたナンパから始まった出来事が、やがて史上最も壮大で破滅的な対立へとつながっていく。
マリサ・ペニャは不死鳥の系譜にある詩人だ。この本は、彼女自身が道すがら選びぬいたハーブを使い、熟練した時計職人の精巧さと、限りなく繊細な手で編み上げた巣である。感動する者の手の中で燃え上がり、その灰の中からよみがえり、再び感動をもたらす。『灯台守の悲しみ』は、思考にしみとおる雨の本であり、心の奥底に湿り気を残す。その湿り気は、悲しみに歌いかける方法だ。
ベン・クラーク「詩でも小説でもない。これはフィクションではない。我々を生と調和で満たす濃密な人生なのだ」 エリカ・マルティネス「厭世の帝国を離れ、ヘスス・モンティエルは私的な現像室で純粋な心を露わにする。現代のシニシズムとは折り合わない純真さを読者に取り戻させる。彼が強く必要とされるのは当然だ」アルフォンソ・トレシーリャス「彼の詩とその純真さは、ボバンの作品にある生の歓喜を彷彿とさせる。それは無邪気な歓喜ではなく、人間の本質に根ざしたもの、彼の超越した感覚に基づくものだ」
生徒の大半が人工知能によって教育され、ほんの一握りのエリートの子どもだけが教師と直に会う世界は、どのようなものだろう。この小説は21世紀末、教師による教育が特権階級だけのものとなった近未来を舞台とする。メリダでは、小さな古典劇団がローマ劇場とともに、人間の本質を生かし続けるために闘っている。彼らはふたつの教育システムの壁を破り、エリートしか知らない教師のベネシアが、学習意欲まんまんだが、コンピューターを通しての教育しか知らないアルシビアデスに授業をするようしむける。
我々の思考は今も他からの干渉を受けずに残っている最後の領域だ。しかし、その我々の脳を占領して思考を操ろうとする数々の用意周到な攻撃が存在する。しかも、その攻撃には最新の技術と一流の専門家がバックについている。世論を操ろうとする者たちは、自分たちの思い通りに物事を動かすため、人々に特定の感情を一定の割合で的確にもたらす方法を既に把握している。本書が目指すのはその真逆だ。不動の真実と思われるものも実はそうではないことを示すのである。
本当のことだといっても、あまり信用できないこともあるので、トラブルを避けるためには、もしかするとちょっとした嘘に頼った方がいいのかもしれない。しかし、それもまた説得力がないとしたら、もっと大きな嘘、つまり汚くて腐ったような嘘、とってもとっても大きな嘘をつくしかないだろう。でも、本当に本当のことは、どんなにありそうもないようにみえても、遅かれ早かれ明らかになるもの。
3つの物語が交錯する作品。ひとつめは、数回ノーベル平和賞候補になった活動家で平和主義者、婦人参政権運動家のシュヴィンメル・ロージカに、フェミニストのエディス・ウィナーが捧げた未完の本の運命と、20世紀前半における、この非凡なふたりの女性の関係。ふたつめは、トランプ政権の終盤の荒れ模様の政治社会状況を背景にした、現代のニューヨークに移住したバスク人一家の暮らしぶり。3つめは、1970年代、80年代に、革命的な女性たちの傍らで語り手が育った小さな海辺の村における、ふたりの少女の友情の回想。
長年フアン・ホセ・ミリャスの頭には、生命やその起源や進化を理解したいという思いがあった。そこで、スペインのこの分野での第一人者であるフアン・ルイス・アルスアガに、なぜ私たちはこのようなのか、何が私たちを今いる場所までたどりつかせたのかをたずねてみることにした。現実についての古生物学者の知見と、作家の持つ機知や個性的な驚くべき視線が組み合わさって本書ができた。ミリャスからすれば、自分はネアンデルタール人で、アルスアガはホモサピエンスだ。
新たなやり方で人生に立ち向かうための羅針盤となるノート。執筆を通してのパンデミックへの回答。すべてに感染する微細なものによって引き起こされた空前絶後の大異変の後、ひとつの声が熟考し、たくらみ、思い出し、朗誦し、そして祈る。パンデミックによる世界的危機の下に、もっと局地的だが類似の規模、あるいはさらに重大かもしれない別の伝染病がひそんでいる。我々の暮らし方、現実や言葉と我々との関係の病だ。声とは、道理の純粋な実践である。