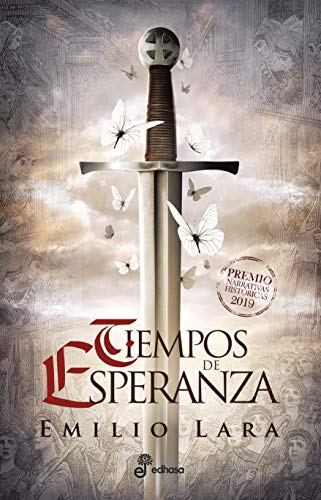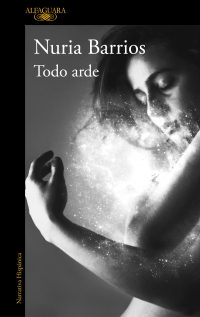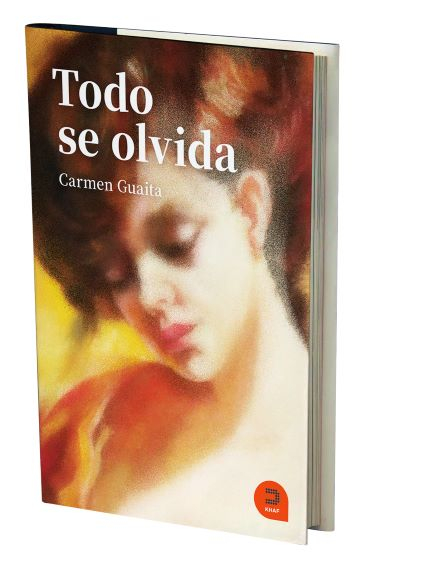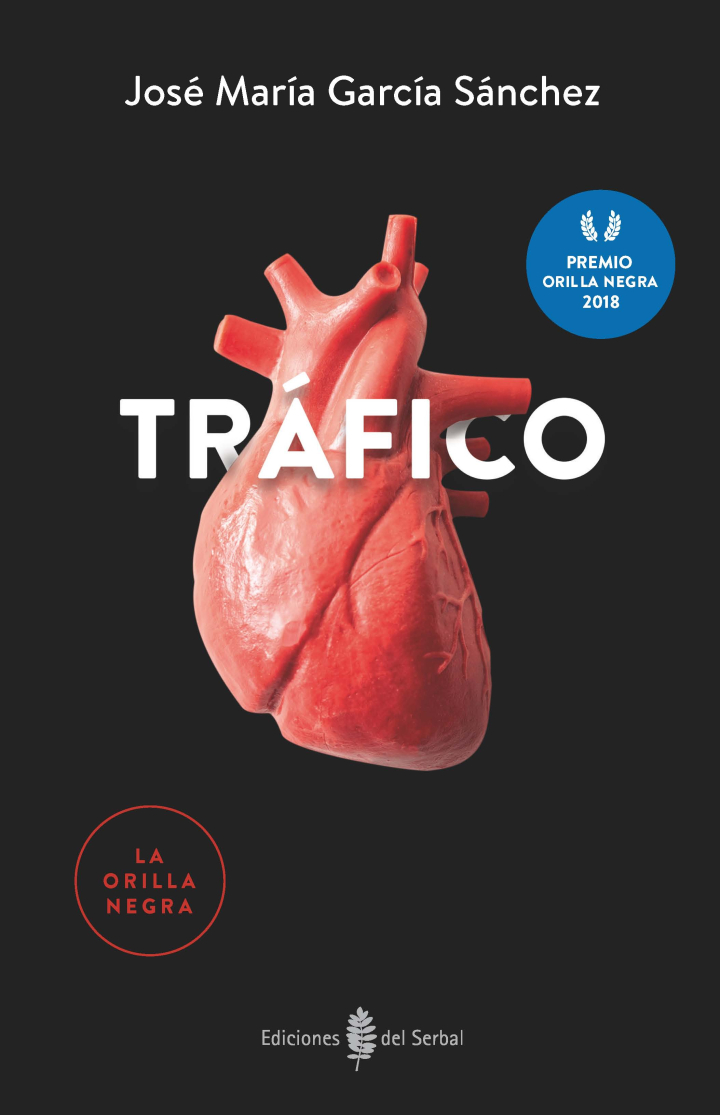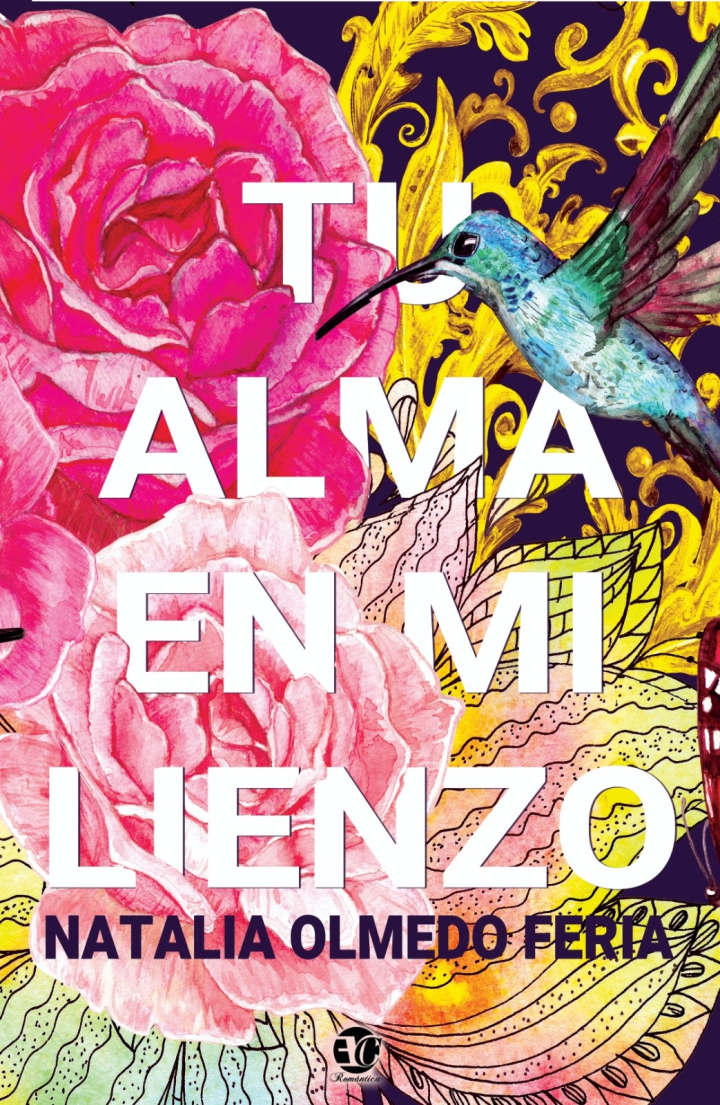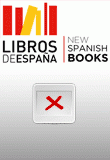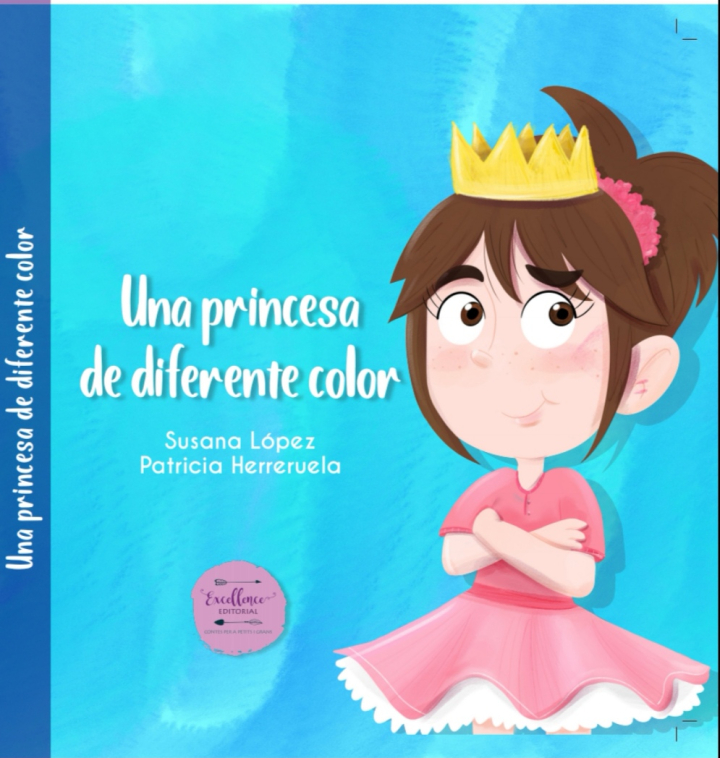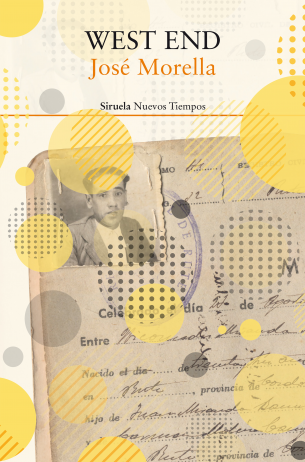スペイン新刊書籍
1212年、主イエス・キリストの年。激動のヨーロッパ。寄せ集められた集団「少年十字軍」がフランス王国を進んでいく。熱狂的で歓びに溢れる雰囲気の中、それを率いるのは羊飼いの少年、クロイエのエティエンヌ。彼らの目的はエルサレム。武器を全く使わず、信仰の力だけで、エルサレムを解放するのだ。一方、ムワッヒド朝カリフ・ナースィルは、戦々恐々の混乱にあるローマに進軍するためセビリアで強大な軍隊を準備する。カリフは、自軍の馬たちに必ずやバチカンの泉で水を飲ませると誓う。
これは姉弟の物語。弟、ロロ、16歳。姉、レナ、クラックとヘロインに溺れている。レナが家を出て1年が過ぎた。ある日、ロロはマドリードのバラハス空港で姉を見つける。彼女はそこで、つまらぬ盗みを重ねながら金を稼いでいた。ロロは自分と一緒に家に戻るようレナを説得しようと、レナが麻薬を買うスラム街についていく。レナはそこに住んでいるらしい。しかし夜が更け、ロロは地獄のような様相をみせる混乱した現実に直面する。
ラ・アロンドラ(ひばり)ことクリプタナ・センシは有名なソプラノ歌手で、長いことアルツハイマーを患っている。彼女の伝記執筆を依頼されたジャーナリスト、ペドロ・ベンナサールは、記憶を失ったひとりの女性の過去を探っていかなければならない。クリプタナ・センシはなぜ記憶を失ったのか? 何を忘れたかったのか? 何を忘れ去ることができたのか? クリプタナがその生涯のうちにやり取りした手紙を発見したとき、ペドロ・ベンナサールは彼自身の人生も立て直すべきだと気づく。
本書はふたりの男の子についての一風変わった物語(ひとりは心臓病を患うブルジョア階級の子弟、もうひとりはスラム街に住む健康な男の子)。彼らの人生が、彼らと彼らの周囲にとって全く悲劇的なかたちで交差する。これは社会派の物語ではないし、ましてや社会を糾弾するものでもないが、この小説はあまりに近くあまりに遠いふたつの環境を描いている。気取って、虚飾に満ち、野心的で、見かけが全てのブルジョア階級。それに対し貧困と暴力に満ちた環境で、生き延びるのに想像を絶する努力が必要な、社会からあぶれた階級。
若きジャーナリスト、カロリーナは、謎めいた有名な画家マルティン・ベラへのインタビューを依頼される。世間ではこの画家は死んだと思われていたが、彼の絵画作品のうちの1点がプラド美術館に展示され、無から突然よみがえった。マルティンは、インタビュー嫌いだったが、カロリーナの中に何かを感じ、彼女のインタビューを受けることを承諾し、ついには長い間闇に包まれていた家族の大きな秘密を告白する。若きカロリーナにとっては、このインタビューは、彼女の人生を大幅に変えることになるだろう。
友情や虚栄心、外見で人を判断しないことの大切さについての物語。森にひとつの小さな包みが現れる。動物たちは誰もが自分宛てのものだと思う。しかしみんなの予想に反してその不思議な小包は小さなトガリネズミに宛てたもので、中にはみんながアッと驚くようなものが入っていた。
ガブリエルとトニは9歳の夏休みに、家族と過ごすキャンプ場で出会った。ふたりは仲良くなり、また、同じ学校に進学したことから互いが親友といえる存在になる。しかし次第にふたりの友情は壊れ始める。果たして正義のためならば暴力に訴えることは許されるのか。トニの反対にあっても、ガブリエルは許されると信じ、それを証明しようとする。「覆面をした男がどこからともなく現れ火炎瓶を投げた。一瞬時間が止まった。人々は息を止め、騒音は掻き消えた。
ひとつの伝説から生まれた主人公の物語。フェリペ5世の時代、レティロ宮殿の庭師たちの間で、植えた花を変えてしまう小妖精の存在が噂になっていた。この物語の小妖精は不機嫌に目を覚ました。本来の陽気さを取り戻すために旅に出ることにする。旅の目的は、その多種多様性の中にすべてを美しく吸収する芸術のおかげで達成する。ユネスコの世界文化遺産に登録されている、計り知れない文化的価値と自然とが融和する空間であるレティロ公園・プラド美術館に収められたコレクションに関するシリーズの第一弾。
主人公の女の子は、父親にとって生まれたときからピンク色の王女さまだった。だけど女の子は、ピンクが好きだと思ったことがない。大きくなってお父さんにそう言うようになったし、おばあさんも説明してくれたが、どれほど言ってもお父さんはわかってくれない。ある日、女の子はいいことを思いつく。お父さんに眼鏡を買ってあげたのだ。それはあらゆるものが見える特別な眼鏡だった。お父さんがその眼鏡をかけると、娘が何年も前から言っていたことをようやく理解した。娘は王女さまだ、が、色については間違っていた。
本作で、ホセ・モレリャは、祖父ニコメデスの人生を振り返る。ニコメデスは、精神病を患ったが、当時その治療や扱いはフランコ主義の時代特有の非人道的なものだった。ニコメデスについて話すことは常にタブーで、親族の集まりでもそれに触れる者はなかった。ホセ・モレリャは、わずかな手がかりを頼りに家族の数人から話を聞きだすことに成功し、祖父の人生に関するとても感動的で勇気ある物語を紡いだ。本書はまた、70年代スペインの生々しい証言にもなっている。