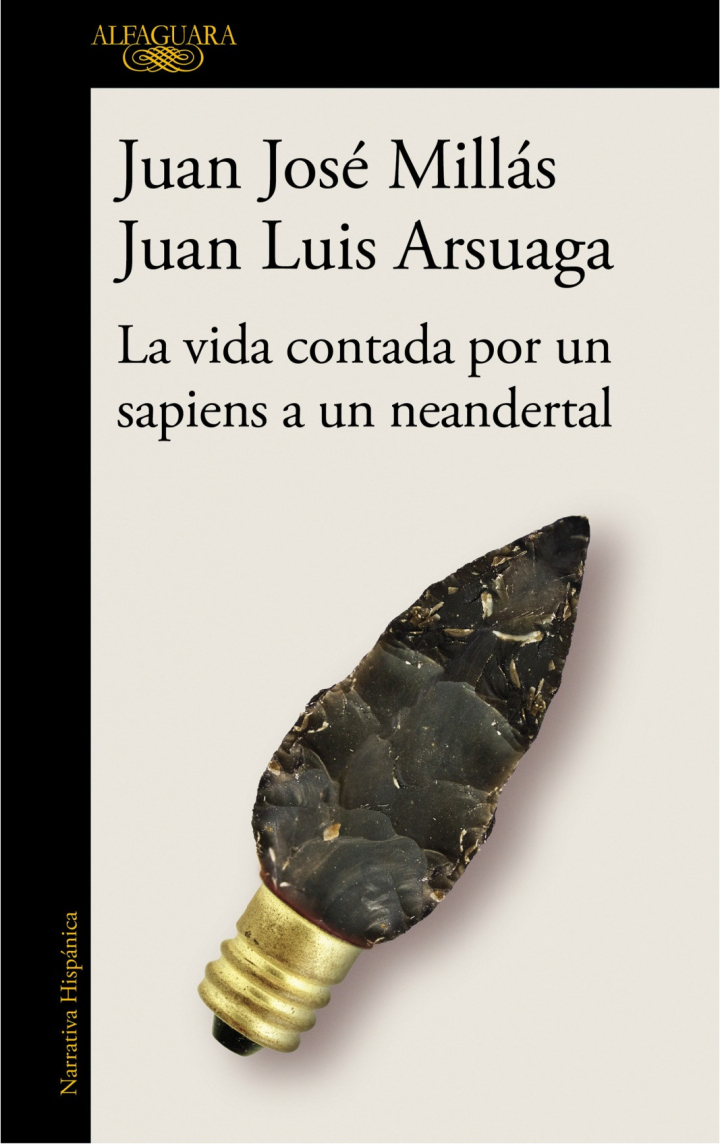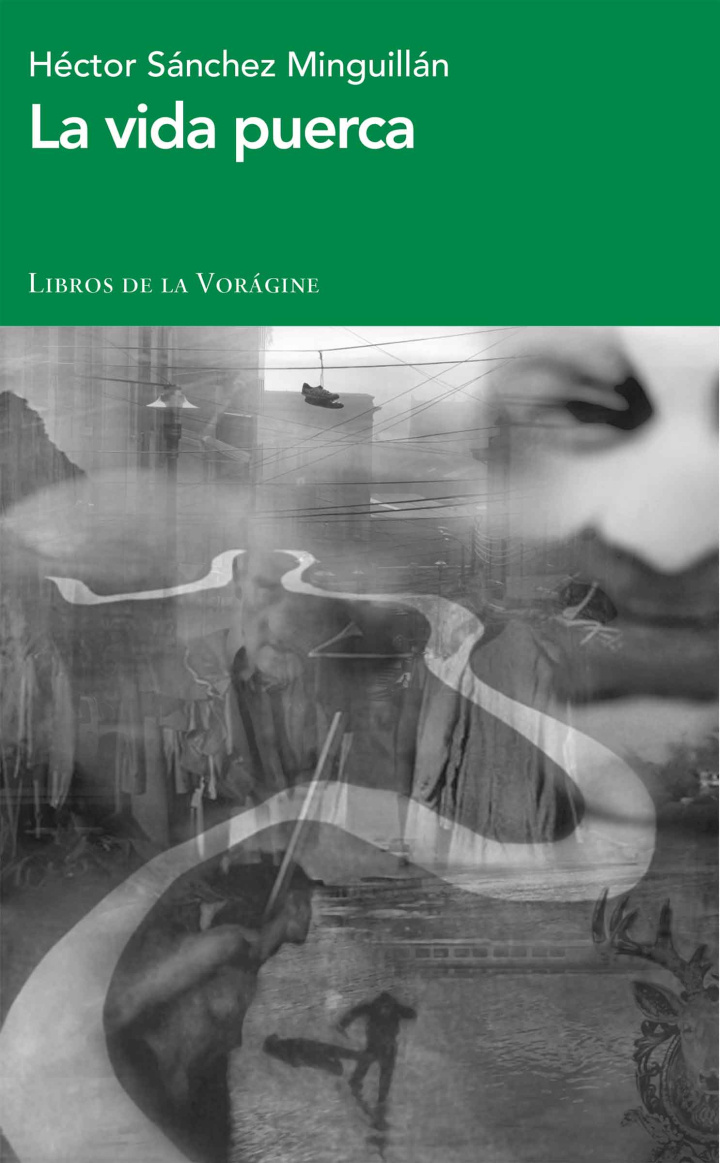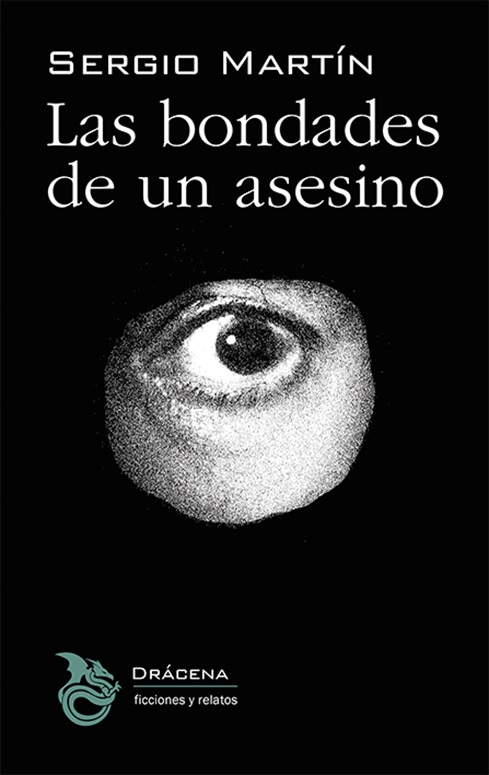長年フアン・ホセ・ミリャスの頭には、生命やその起源や進化を理解したいという思いがあった。そこで、スペインのこの分野での第一人者であるフアン・ルイス・アルスアガに、なぜ私たちはこのようなのか、何が私たちを今いる場所までたどりつかせたのかをたずねてみることにした。現実についての古生物学者の知見と、作家の持つ機知や個性的な驚くべき視線が組み合わさって本書ができた。ミリャスからすれば、自分はネアンデルタール人で、アルスアガはホモサピエンスだ。
新たなやり方で人生に立ち向かうための羅針盤となるノート。執筆を通してのパンデミックへの回答。すべてに感染する微細なものによって引き起こされた空前絶後の大異変の後、ひとつの声が熟考し、たくらみ、思い出し、朗誦し、そして祈る。パンデミックによる世界的危機の下に、もっと局地的だが類似の規模、あるいはさらに重大かもしれない別の伝染病がひそんでいる。我々の暮らし方、現実や言葉と我々との関係の病だ。声とは、道理の純粋な実践である。
プリミティボ・ダトロが作家マウロ・レデスマ=ペリスの筆耕者を募集の広告を見て応募したとき、自分が恐怖の迷路に入りこみつつあるとは思いもしなかった。作家の蛮行にあった後、プリミティボは他の被害者の証言を集めた証言集を作ることにする。こうして生まれたのが『下劣な人生』だ。その残忍な行為をなんとか逃れた者たちの話を通じて、レデスマ=ペリスの人生と人間性を浮き彫りにした本だ。エクトル・サンチェス=ミンギリャンは本作で、倒錯したナルシシストの人となりと、ねじれて混乱した誘惑のやり口を巧みに描きだす。
11歳の女の子、ウルスラの生活はちょっと複雑。何度も小学校をかわり、母さんはメトロポリタン美術館から絵を盗んで、逃亡生活を送っている……。ちがう……、そうじゃない。ウルスラはレベッカと名乗る11歳の女の子で、母さんを消してしまった魔法使いたちが大嫌い。それともレベッカは有名なスパイで、追跡をかわすためにウルスラと名乗っている? まあ、いずれにしても11歳で、箱のなかの5匹のミミズと、宇宙で迷子になったネコを飼っている。
今日誰がサラ・アマットのことを憶えているだろうか? ある夏の夜、行方不明となったとき、彼女は13歳かそこらだった。以後何もわかっていない。ただ、翌日タラサ新聞にニュースが出て、多くのうわさや憶測が飛びかっただけだった。だが、この物語の語り手である、サバテール家のペップは彼女のことをよく覚えている。というのも、彼の話によれば、サラはその夜、姿を消したのではない。彼の家に裏口から忍び込んだからだ。
ライモンはラジオのために物語を書き、弟のブライと一緒に暮らしている。ブライは小さいころ森で起こった事故のせいで情緒不安定だ。今は作業所で働きながら質素な暮らしをしている。ある日ライモンは、いつも彼の物語をラジオで聞いているという年配の女性セリアから奇妙な依頼を受ける。彼女の回想録を書くために彼を雇いたいというのだ。「あなたの物語が私の人生をこんなにもうまく説明してくれるとは想像もしませんでした」。その女性は、自分の全人生を再現して書いてほしいと頼む。
家で一番小さな子の部屋に、夜ごとひとりの客が現れ、恐怖からか感動からか、その子を震え上がらせる。マルガリータの文とナタリア・コロンボのイラストが最後まで興味を持続させつつ、なんだかわからないもの、立ち向かわなくてはならないコントロールできない物や状況に対する子どもの恐怖心を描く。サスペンス調の楽しい語りは、子どもたちをひきつけずにはおかない。
中国の女性エコロジスト、ペルーの男性シャーマン、ニュージーランドのマオリ族女性、ロシアの女性宇宙飛行士の卵…。共通点は何だろう? 悩みは何だろう? どんな暮らしをしているのだろう? どんなふうに将来に立ち向かうのだろう? これはジャーナリスト、マルク・セレナが1年間にわたって世界一周をし、25か国の同年齢25歳の若者25人とともに暮らしながら問いかけた質問である。
1916年、フランス・ヴェルダン。第一次世界大戦が勃発したとき、イレーヌ・キュリーは可能な限り前線に近づこうとした。多くの命を救うことに役立つことを信じ、彼女と母親のマリー・キュリーが考案したポータブル機器を使った放射線医学を野戦病院の外科医たちに伝えようと努める。バールルデュックの病院に滞在し、兵士、医師、同僚たちの尊敬を勝ち取るために闘いはじめた。ドイツ軍がヴェルダンを爆撃し、命を救うためのタイムトライアル・レースがスタートした。
辛口でむさ苦しいパロディー、下品で時に不敬な言葉遣い、全てにおいて腹立たしい、イギリスの田舎町での出来事。そのどれを取っても、本書『Las bondades de un asesino(ある殺人犯の親切心)』はガイ・リッチーや ダニー・ボイルの素晴らしいコメディ映画を彷彿させる。しかしこの小説の結末には物悲しいパラドックスが隠されていて、それはスペインの良質のユーモアのなかにはなかなか根付かない流れだと言えば不興を買うかもしれない。