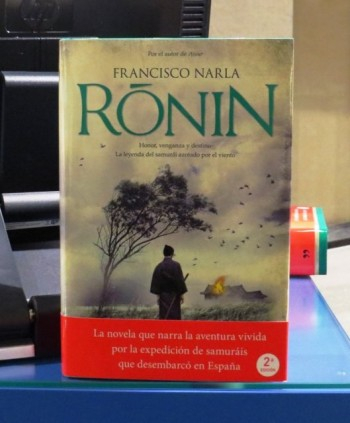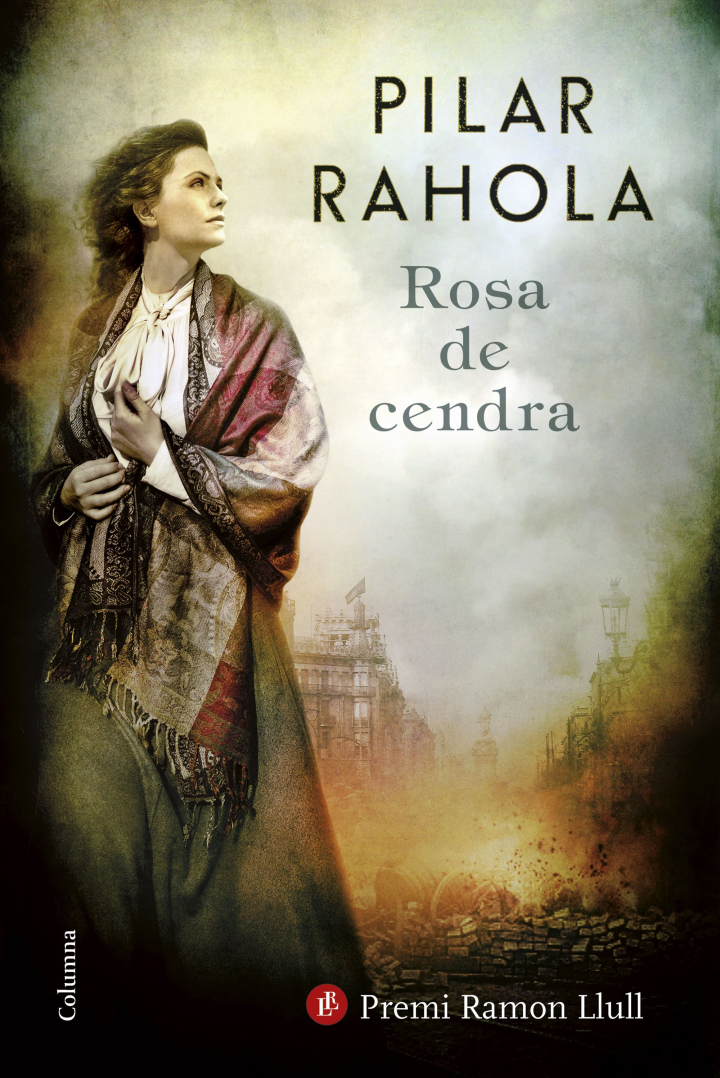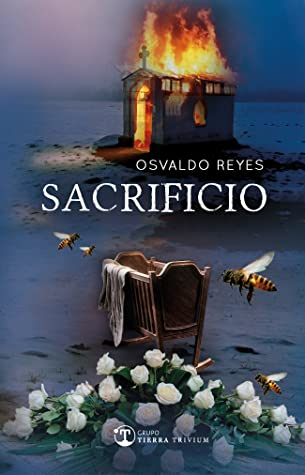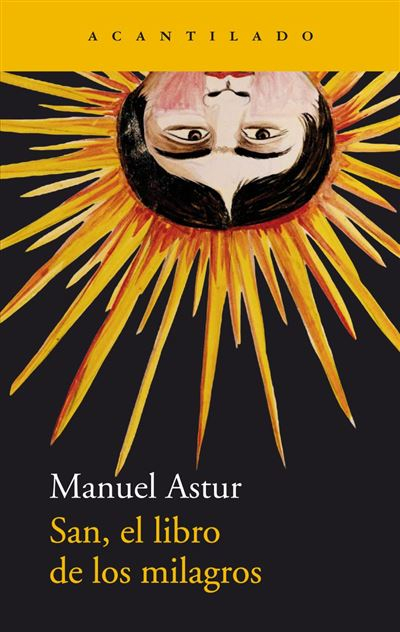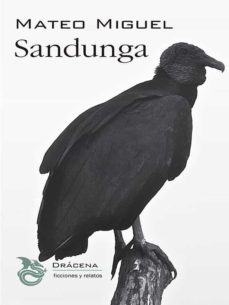成熟したひとりの女性が、思い出の中で自分の人格の跡を追い求める。時間の経過のもたらした喪失と獲得物をうけいれ、人生に求めることができるものとできないものを見分けることを知る。苦境から自分を救うすべを学ぶ。いない者たちの不在を認める。愛の絶対的価値を信じないが、最後のチャンスを与える。ほかの女性たちの苦悩や恐れを知る。皮肉な息遣いを保つ。そして、孤独のなかに成長し続けるためのはずみを見つける。時には、よきものが私たちを傷つけることがないように風を見張りながら火を焚く。
友人との食後のおしゃべりのように楽しいが、肝臓につきささる鉤爪のような打撃を与える小説。敵から〈カバ〉と呼ばれている、主人公のバシリオは、その相反する性質をいくらかかかえている。119キロの巨体の彼は、そのあだ名を喜んでいる。機会をねらってじっと動かないカバの沈着さは彼のめざすところであり、またカバの獰猛な性質、攻撃的本能、とんでもない知性が彼をひきつける。
E. M. フォースターの言葉によると、小説においてはたとえば、悲しみというたったひとつの言葉がストーリーとプロットを分ける。悲しみがプロットをつくるのだ。本書『Ramona(ラモーナ)』は幼年期から青年期への移行を、その過渡期に生じる特有の悲しみを通して描いた物語。その描き方のためだろう、主人公も彼女を取り巻く登場人物たちも読者の同情に訴えかけようとせず、贖罪を求めている風でもない。ロサリオ・ビリャホスがつくりだす世界では、ヒロインの旅は、通行料を払う手段さえ持たないことを知る人の旅だ。
ベッドタイムの母と子の対話の本。だがこれは、日中いつでもどこにでもある親子のやりとりではない。
名誉、復讐、そして運命。時代の波にもまれた侍の物語。時は1600年、大海が国々を鍛え男たちを静めていた時代、フィリピンを目指して航海中のテルシオ軍の少尉ダマスコ・エルナンデスは出世して女官コンスタンサと結婚することを夢見ていた。同じ頃日本は群雄割拠の世。後に伝説となる長期に渡る包囲戦が行われていた伏見城では、4万の兵を率いる敵軍に対して、ほんの一握りの強者が城を守っていた。名誉の最期を遂げるには最早切腹しか無いと思われたその時、大将がその中のひとりに切腹を諦めさせ、ある任務を命じる。
キューバ戦争からすでに多くの年月が過ぎた。貧困と不幸に打ちひしがれた兵士だったアルベルト・コルネル=イ=エスピガはもう二度とみじめな思いをすることはない。彼は生き残り、新たな男になったと感じた。その予感通り富を築いてカタルーニャの上流階層と交流し、裕福な家庭をもった。時は政治的に不安定でいつ火花が散ってもおかしくない状態にあった。1901年の選挙ではカンボとプラット=ダラリバ率いるリーガ・ラジウナリスタが勝利。王党派とレルー派は暴動を起こし、政府がさらに追い打ちをかけた。
悪は不意に忍び寄ってくる。8月のある寒い夜、そのことをエバンス一家は身をもって経験することとなった。闇の中、娘のサラが二人組の何者かにさらわれ、姿を消したのだ。彼女は生きているのか、刑事アンへロ・モリスと法心理学者ハミレン・ラッソは力を合わせ、時をさかのぼって事件のなぞに挑む。一貫性がなさそうに見える犯罪にむきあうふたりは、犯人が残した手がかりが30年以上前の未解決の謎を指し示していることに気づく。
「マルセリノは作業を止めて立ち上がると、手の甲を額にかざし足元の谷を見つめた。何もかもが金色の光の鈴のようにきらきら輝いていた。7月のあの日も同じようにマルセリノは立ちすくみ、じっと目を凝らしていた。家屋も穀物庫も荷車も夕暮れの濃い藍色に包まれる中、ただ弟から流れる血痕がおがくずを赤く染めていた。彼は弟を傷付けるつもりなどさらさらなかった。空には新たな時代の幕開けを告げるように一番星が輝き出していた。
「毎日の我らの酒よ、昼も夜も我らを見放すことなかれ」毎朝サンドゥンガはこう唱え、その日の最初の酒を1杯飲むと、気の向くまま過ごすために家を出る。欲望も目的も持たず、流れ任せの人生だが、それ自体がこの面白い小説の筋になっている。あるひとりのメキシコ先住民があるがままに世に出るが、様々な出来事に巻き込まれる。素晴らしくもない日常のせいではないが、大抵の場合不幸な出来事だ。
本書は、従来のドラゴンとおひめさまの物語とは少し違う。主人公のおひめさまは、なんとふたつの城に住んでいる。ひとつ目の城では、母親と義理の父とたくさんの家族と一緒に住み、もうひとつの城では父親と義理の母親(意地悪なまま母とは似ても似つかない)と住んでいる。ふたつの城の間を毎週自転車で行き来するのだが、仕事をリタイアしたドラゴンが耕す小さな野菜畑を自分が走っているとはおひめさまは気づいていなかった。