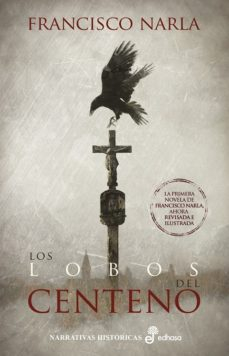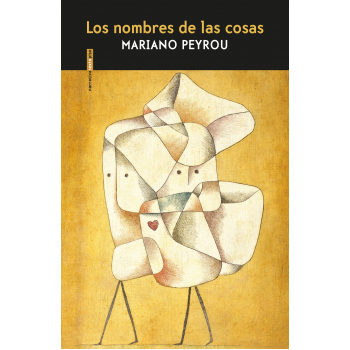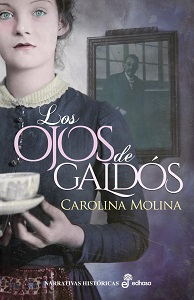メキシコ・シティ。女優のパメラ・ドサントスは、その有名な太ももと、メキシコの大物政治家たちが通り過ぎて行った広く寛容な心のおかげで、スターの座に上り詰めていた。だが、彼女のバラバラ死体が発見されると、続いてPRI(制度的革命党)の政権復帰に赤信号をともすわけのわからない出来事が次々に明るみにでる。トマスは、全くやる気のないジャーナリストだが、この有名な女優の殺人について急ぎ記事を書き、死体発見現場について、必要な裏付けをせずにあるデータを盛り込む。
家族と週末を過ごしていたベビラクア曹長は、レバンテのある場所で女性町長の死体が発見されたという知らせを受ける。町長の夫がかねてから妻の失踪を届けていたのだが、死体はビーチで観光客に発見されたのだった。ベビラクアと部下たちが到着し、捜査にとりかかった時には、既に判事が死体を引き上げ、最初の方策は講じられ、葬儀の準備が行われていた。現場はごたごたし、被害者についてありとあらゆる噂が広まっていた。
仕事にも結婚にも疲れた新聞記者のルイスは、テキサスのオースティンでの学会に出席する予定である。出張は、人生の唯一の喜びとなっているカミーラとの束の間の逢瀬のアリバイにすぎない。しかし、出発しようとしたとき、カミーラから「もうここでおしまいにして、思い出にしましょう」というメッセージを受け取る。ルイスは落胆し、どうしてよいかわからないままオースティンに行き、大学の文書館にこもり、そこで偶然、ウィリアム・フォークナーが愛人ミータ・カーペンターに送った手紙を見つける。
1950年1月14日、アスンは才能というよりも図々しさを武器にコプラを歌っているタブラオへ出向いた。その夜、人生を一変させる人と出会うなど知る由もない。その人物とはアテネオ図書館の司書サントスで、文化的な繋がりや大学生との交流を通して反フランコ派レジスタンスに協力していた。このふたりの間に、外見はごくありふれたものだが、実は非常に特殊な関係が生まれる。サントスはアスンに文学を通した自由と変革の可能性について教え、彼女は見せかけの婚約関係で彼の隠れ蓑になった。
深く魅力的な文体で、恋をした状態について考察する小説。ほぼだれもが恋愛を有益なもの、ときには救済とさえ考えるがゆえに、恋愛においては、高貴で無欲な振る舞いから、大いなる横暴や下劣さまで、ほとんどすべてのふるまいが正当に思えるものだ。
ムルシア、サン・フアンの夜。3人の登場人物が経験する忘れがたい物語。メキシコ人のハシントはドン・ホルヘのボディーガード。ボスがパーティに興じている間に、身内を殺した殺し屋たちと決着を付けなければならない。マリアはその夜新しい経験をして家族のゴタゴタを忘れたいと街に出かけて来たティーンエージャーの女の子。ハシントとマリアが出会う。
2011年春に政党の閉鎖性に対抗して起こったスペインの若者たちの抗議デモ、15-Mから10年を記念して出版された。物語はデモの1週間前に始まる。しばらく世間から離れて入院し、退院したばかりの主人公のモイセス・マルメロは、勤務していた会社はどうなっているか確かめようと出かけ、最後にデモの参加者が溢れるプエルタ・デル・ソル広場にたどりつく。章を追うごとに、当時のマドリード、そしてスペインの姿の忠実でユーモラスな描写へと変貌していく本書。
ガリシア内陸部の村で、気難しいやもめの風車守の男が、ガリシアに伝わる最悪の悪夢が周囲で息を吹き返すのを目の当たりにする。バラバラになった動物の死骸が発見され、収穫作物が荒らされ、亡霊行列(サンタ・コンパーニャ)が現れ、狼男が代父を襲う。村人はそれらを風車守のせいにし、村のメイガ(霊媒師)がしゃしゃり出てくることで、村人の間の裏切りの歴史が暴露されていく。本作は、著者フランシスコ・ナルラの処女作で、主人公たちの暮らしだけでなく、死、残虐性、欺き、魂の悲嘆についても、正確かつ豊かな表現で語る。
毎週木曜日、3人の友人がバルで集まる。ひとりは映画監督で現実と想像の世界を隔てる境界線を常にあいまいにしているようにみえる。もうひとりは小説家で、書くことと生きることにおいてできる限り自由であることを目指し、文体もガールフレンドもあまた持つ。3人目はある役所勤めの公務員、自分の妻や息子のことをほとんど何も知らないと感じている。
貧しく、病気がちで、ほとんど目が見えない。スペインが生んだ20世紀文学の天才、ベニート・ペレス=ガルドスはそんな風に晩年を生きた。それにも拘わらず、彼は友人、家族、市井の人々からの愛情に不足することはなかった。彼が文筆業を続けるために他の若い人たちの目に頼ることが必要になったとき、彼女、カルメラ・シッドが彼の傍らにいた。彼女が彼の目になる。そして彼の声になる。