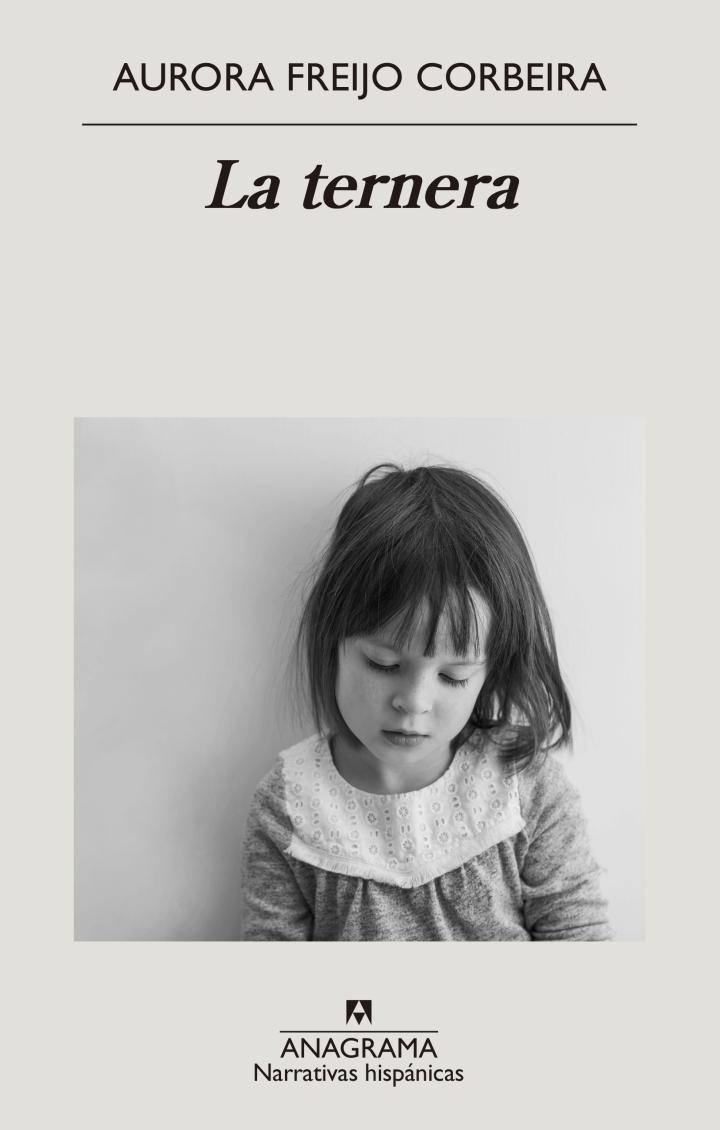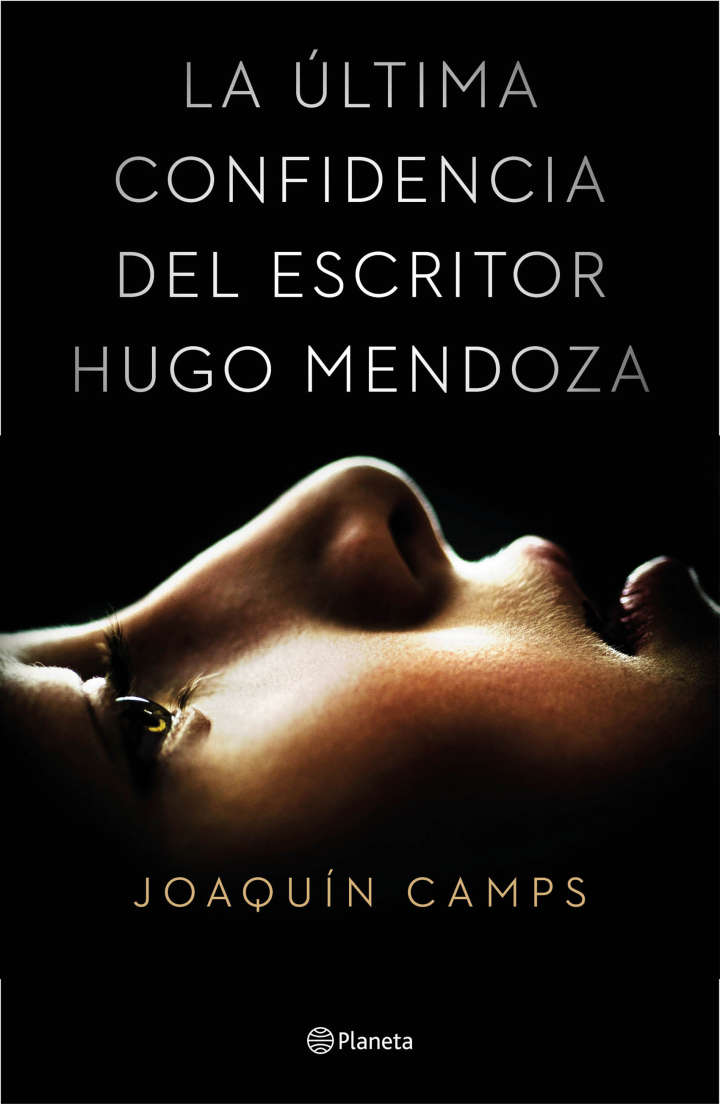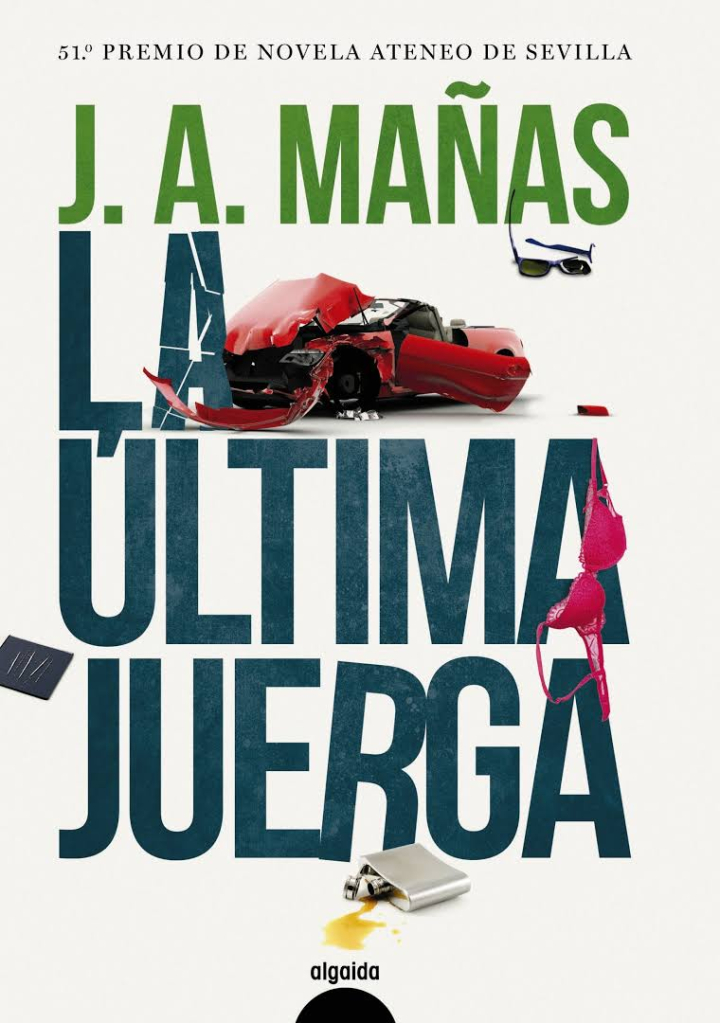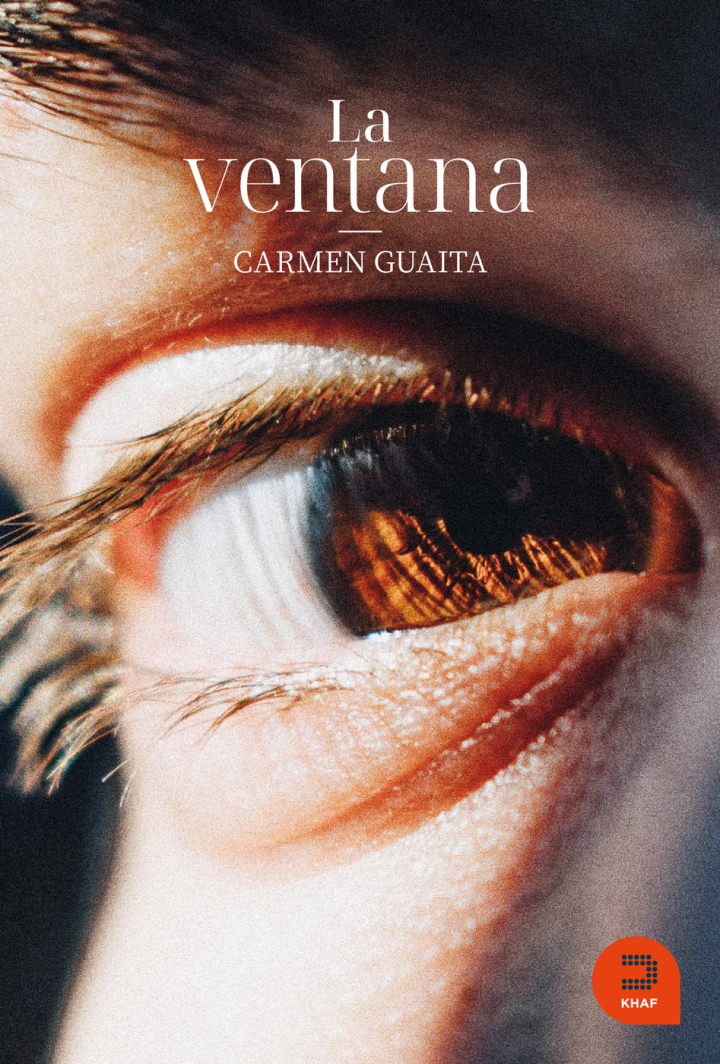幼女に対する虐待を圧倒的な文学の力をもって語る。いたたまれない内容だが読むべき本。たったひとつのしぐさで彼女は子牛と化した。その子はあまりにも幼くて、自分が不自然な立場に置かれている事さえ分からない。深い絶望を秘めた瞳と驚きを隠せぬ眼差し。自分の家には居場所がなくなった。親しくしている隣人はまだ適齢に達してもいない彼女を肉として初めて味わった。孤独だけが彼女に残った。『La ternera(子牛の肉)』は誰もが目を背けていたい虐待の現実を、抑制のきいた筆致で語る。
モートンハムステッドはイギリスで一番長い名前の村だが、あるとほうもないことで知られている。メアリー・ジェイの墓に秘められた伝説だ。ある晩、11歳のジョン・ウィルコックスといとこたちは、伝説の秘密を明かそうと、墓のところでキャンプすることに。その夜は、ジョンが想像もしなかった長い夜となり、おそろしいたいへんなことが起こる。どんなことか、知る勇気はあるかな?
モートンハムステッドはイギリスで一番長い名前の村だが、あるとほうもないことで知られている。メアリー・ジェイの墓に秘められた伝説だ。ある晩、11歳のジョン・ウィルコックスといとこたちは、伝説の秘密を明かそうと、墓のところでキャンプすることに。その夜は、ジョンが想像もしなかった長い夜となり、おそろしいたいへんなことが起こる。どんなことか、知る勇気はあるかな?
マリサ・ペニャは不死鳥の系譜にある詩人だ。この本は、彼女自身が道すがら選びぬいたハーブを使い、熟練した時計職人の精巧さと、限りなく繊細な手で編み上げた巣である。感動する者の手の中で燃え上がり、その灰の中からよみがえり、再び感動をもたらす。『灯台守の悲しみ』は、思考にしみとおる雨の本であり、心の奥底に湿り気を残す。その湿り気は、悲しみに歌いかける方法だ。
1941年、スペインのエストレマドゥラで起きた犯罪がアルカラ家の家族3代と、40年間彼らと関わりあった人々に影響をもたらす。陰謀、誘拐、殺人、拷問、男性から女性への暴力などをもりこんで、小説は展開する。著者は、ルポルタージュ的かつ軽快な文体で、起こった出来事を語り、登場人物ひとりひとりの心理に入り込みながら、少しずつ双方の人々を絡み合わせていく。その結果、感情と遺恨、愛と憎しみ、野望と苦悩、偽善ととりわけ罪悪感が渦巻く素晴らしい推理小説となった。
地下鉄のトンネル工事を進めていた掘削会社の責任者である若きエンジニアが、忽然と姿を消した。これが、私立探偵フェルミン・エスカルティンが立ちむかう、身の毛のよだつ事件の始まりとなる。大学教員から探偵に転身したフェルミン・エスカルティンは、フェルナンド・ララナのミステリーシリーズの主人公。『トンネル掘り』は中でも、鋭い皮肉と真に迫る恐怖が冴えわたる、一度手にとると最後まで一気に読まずにいられない秀作ミステリー。
魅力的な文学教授ビクトル・べガは、作家ウゴ・メンドサの未亡人からの風変わりな依頼を引き受けることにする。ウゴ・メンドサが死んだことは厳格に証明されているのだが、彼女は、亡き夫がまだ生きていないかどうか、毎年12月3日に彼の新しい手稿を送ってくるのが誰なのかを調べて欲しいと頼んできた。ビクトルは謎の糾明に乗り出し、その結果、自分の生命を脅かされるようになるが、一方でその間現れた謎めいた美女にぞっこんになる。
当時彼らは20歳を少し過ぎた頃だった。クローネン・バルに集合して、セックス、アルコール、ドラッグで若いエネルギーを発散していた友達グループ。ときには、命を危険にさらすほどの馬鹿をすることもあり、そのおふざけが過ぎてとんでもない結果を招いた者もいた。それから長い時が経った。ちょうど25年だ。今彼らは仕事をし、暮らし向きも悪くない。結婚して、子供がいる者もいる。ドラッグをやる者はほとんどいないし、酔っぱらってどんちゃん騒ぎをする代わりにワインをたしなんでいる。
生徒の大半が人工知能によって教育され、ほんの一握りのエリートの子どもだけが教師と直に会う世界は、どのようなものだろう。この小説は21世紀末、教師による教育が特権階級だけのものとなった近未来を舞台とする。メリダでは、小さな古典劇団がローマ劇場とともに、人間の本質を生かし続けるために闘っている。彼らはふたつの教育システムの壁を破り、エリートしか知らない教師のベネシアが、学習意欲まんまんだが、コンピューターを通しての教育しか知らないアルシビアデスに授業をするようしむける。
3つの物語が交錯する作品。ひとつめは、数回ノーベル平和賞候補になった活動家で平和主義者、婦人参政権運動家のシュヴィンメル・ロージカに、フェミニストのエディス・ウィナーが捧げた未完の本の運命と、20世紀前半における、この非凡なふたりの女性の関係。ふたつめは、トランプ政権の終盤の荒れ模様の政治社会状況を背景にした、現代のニューヨークに移住したバスク人一家の暮らしぶり。3つめは、1970年代、80年代に、革命的な女性たちの傍らで語り手が育った小さな海辺の村における、ふたりの少女の友情の回想。