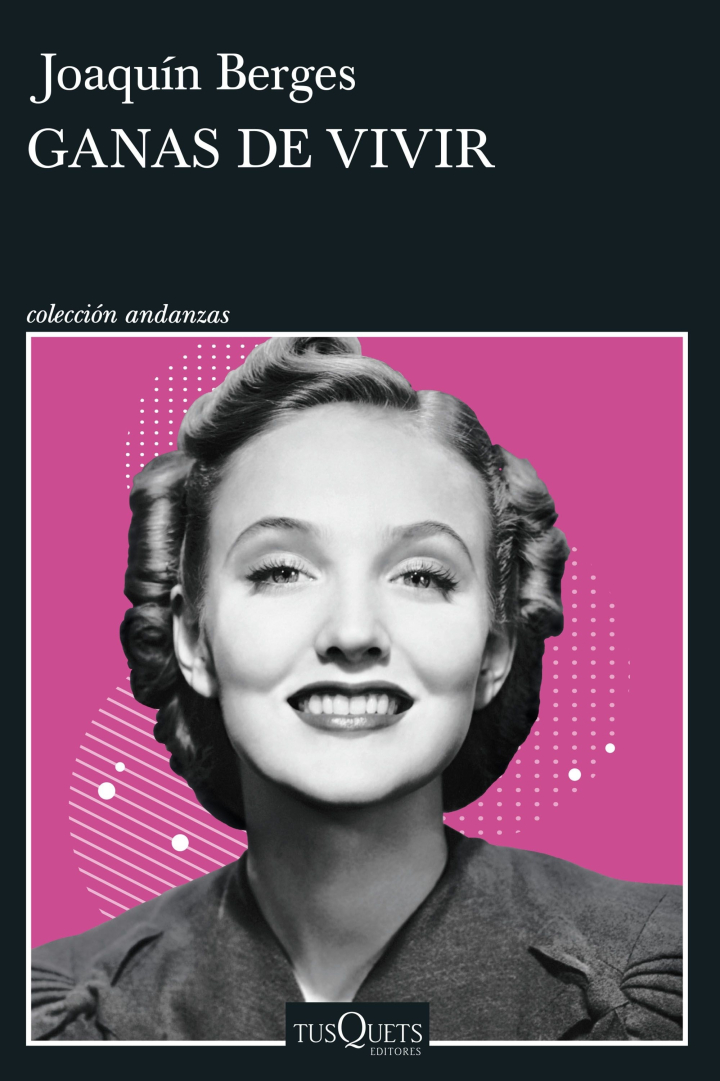フェデの一番の望みは海賊になることだが、海賊への道は遠い。海賊になるためには、その前にやっておかねばならないと思われるいくつかのことがある。たとえば、ひとりでおふろに入ること、ベッドの中でこわがらないこと、オウムを手にいれること、そして何より重要なのは片脚をなくして、義足をつけること。しかし、クラスに転校生がやってきてから、勇敢な海賊になるには、脚をなくさなくてもよいことがわかってくる。
フェリペはかぜをひいていて、くしゃみが止まらないけど、薬をのみたくない。だけど、友だちが教えてくれるなおし方はどれもむちゃくちゃで、ちっともなおりそうにない。だからかわいそうに、フェリペはかぜをひいたまま! この絵本に出てくるフェリペは、かぜをひいてもおばあちゃんには耳をかさず、友だちのいうことばかり聞く。経験ゆたかな人の言葉には、教えられることがたくさんあるのにね……。
古くからの友人たちの一行が、山小屋に集まって週末を過ごす。彼らには、過去の暗いひとつのエピソード以外には共通するものは何もない。集まりはいつもの筋書き通りに進行するが、宴たけなわの中、外部からのある出来事で、すっかり計画が変わる。
1977年6月、思春期を迎えて間もないフアンとロサは、ポルトガルとの国境沿いの道路を非合法の堕胎手術を行う病院へ向かっていた。しかし事故に会い目的地へ着くことはなかった。それから20年ほどたち、ロサと息子のイバンは新たな人生を歩むためにイベリア半島の反対側の突端の地に移り住む。だが、過去は否応なしに追いかけてくる。時には害毒でしかない強い血縁、世代が変わっても同じ過ちを繰り返す危険が潜む家族の秘密、そして人を別人に変えてしまう知恵について書かれた小説。
1874年10月。ガブリエル・カマラサは、ロンドンで数年の亡命生活を送ったのち、家族とともにバルセロナに戻ってきたばかりだ。ラ・ロンハ建築専門学校の初日、入学2年目の若者アントニ・ガウディと知り合う。若いカマラサにとってガウディは謎だ。その年齢の建築学生には考えられないほど豊富な建築の知識を持ち、秘教とオカルト植物学と写真にも興味を寄せる。また、バルセロナの最下層の人々とコンタクトを持ち、彼らと謎の商売をしている。ガウディはまた一級の演繹的思考の持ち主である、あるいはそう考えられている。
葬儀業を営むロレンテ一家は、代々まともだと感じさせない強迫観念的な固定観念を受け継いでいるようだ。生き埋めにされる恐怖は、祖父の化粧品で増すばかりだ。父親のマティアスは、葬儀屋に持ち込まれた美しい女性の遺体に密かに惹かれずにはいられない。そして孫のトリスタンはちょっとしたフェティシズム気質だ。映画発祥の地ハリウッドの美人女優を彷彿とさせるグレースと恋に落ちたトリスタンは、生きる気力も幸福感もない、普通とはかけ離れた人々に囲まれていることに気づく。私は心配だ。
ガリシアの農村で暮らす3世代家族のユーモアに満ちた愛情深い小説。離婚したばかりのジャーナリストのフリアはマドリードを離れ息子のセバスと故郷のガリシアに戻ることにした。転地で心を癒すため、また母親の面倒を見るために決心したことだった。10歳のセバスは祖母のルスを神のトールと信じて疑わない。なぜなら、彼女は片時も愛用の金槌を手放さないからだ。しかし、たとえお菓子のポルボロンを靴下に隠そうが、物が二重に見えるようになるまでワインを飲もうが、嘘ばかり言おうが、セバスは祖母をとても愛している。
とても変わったひとりの人物の物語。自分の居場所を求めて世界をめぐるうちに、たくさんの冒険に出会う。
シュールなノワール、突飛で凄まじい純正のコメディ。著者がまたしても舞台に選んだのは独特な街マドリード。主人公はカストルのあだ名で知られるコメディアンで、テレビで演じるひとり芝居が有名。成り行きと運任せの人生だが、その運に導かれ、彼とよく似たフリオという名のウェイターと知り合う。ふたりは瓜二つだった。そこでカストルは大嫌いな夜会にフリオを自分の代わりに行かせることを思いつく。しかし事はうまく運ばず、過激で気も狂うような出来事が次々と起こる。
マリオが急死した。妻カルメンは通夜の夜、ひとり、亡き夫に向かって5時間にわたって語りかける。その間、マリオはじっと沈黙を守る…。しかし、彼は死んだからといって妻の独白に耳を傾けるのをやめはしない。肉体はないが、彼は完全に状況を理解している。そして今度はマリオが戻ってきて、夢の中でこたえる番だ。