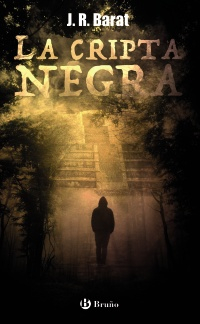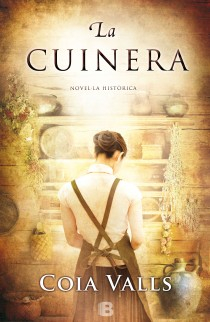本書はサラマンカ大学という組織の初期の歩みを描いたものである。サラマンカ大学の創設は12世紀だが、カトリック女王イサベルが同大学をソルボンヌ大学スペイン版に育てようと決心して世界的に有名になった。本書は見事な散文によって、魅惑的で激しい世紀に我々をいざなう。人文主義がイタリアでおこり、ヨーロッパに広がった後スペインにも到来した時代である。イベリア半島では、すでに確立している宗教秩序を維持せんと人文主義に対抗し異端審問所が立ちはだかる。
校内のトイレでガラスの割れる音がした。カルロスは激しい音にハッとして、すぐさま駆けつけた。すると、学校一完璧な女の子、エステル・サンチェスが床に倒れ、頭にひどいけがをしていた。カルロスは、彼女のそばで思いもよらない奇妙な物体を見つけ、すぐポケットにしまい込んだ。その瞬間から、カルロスは不思議な冒険に巻きこまれ、何もかもが見た目とは違ってくる。ファンタジーと青春恋愛ストーリーの要素のもりこまれたミステリー仕立ての小説。現代社会における科学の限界について考えさせてくれる。
2、3本のかなりさびれた通り、それだけがハバナのチャイナタウンの名残だ。キューバ人の元刑事マリオ・コンデはそこに足を踏み入れた途端、何年も前、1989年に既に来たことがあるといやでも思い出す。魅力的な警部補のパトリシア・チオから不思議な事件を解決するために手を貸してくれと頼まれたのだった。ペドロ・クアング老人の殺人事件。老人は指1本が切りとられ、胸に丸と2本の矢の絵を刻んだ状態で、首を吊って発見された。これはサンテリア教(キューバの民間信仰)の儀式だった。
本書はバルセロナのとある出版社でゴーストライターとして働く女性の物語。独特のユーモア感覚で、エンパル・モリネーは驚くべき物語をつくりあげ、その登場人物たちに現代の出版界を浮き彫りにさせる。複数のストーリーがからみあう、ユーモアと皮肉たっぷりの小説。
ベニテス=レイエスの今回の小説はあちこちで集まっては話に興じる物語。パンデミックの真っただ中、5人の陰謀論者が好き勝手に自説を唱え奇想天外な結論を導き出していく。彼らにとって公式発表は明らかに現実を歪曲したものでしかない。毎日流れるニュースに沿って、理性から最もかけ離れた理論に基づき意見を述べ、議論し、もっともらしく話す。科学、地政学、社会経済学に関するどんな問題でも標的だ。全くの作り話のように思えてしまうが、実際の資料に基づいた小説。
よい妖精がついに死に絶える世界を描いた、アクションと冒険に溢れるファンタジー小説。鏡の王都とは、テラリンデ王国の首都であり中心地。この国の妖精たちは、人間が存在するとは思っていない。この古都は「眠れる女王戦争」の間、決定的な役割を果たした。数年前のその血みどろの戦争によって、王国には危うい平和と数々の恨み、不安定な王座が残された。そんな王国で、ニカシアとドゥハルは長年権力を巡っていがみあっている。
ある町に入りこんだ12の命。彼らを生かしておくか、運命にまかせるか、意見が分かれた空想上の生き物たちの都。悪夢か、はたまた奇跡を呼ぶ赤い月の到来を、みなが待っている。
それは、ロカバランコリア王国の最後の希望、王国の失われた栄光をとりもどす唯一の機会。しかし、希望ははかない。30年の間、連れてこられた若者はひとりとして生きのびられなかった。30年の間、ひとりとして生きのびて赤い月を見た者はいない。
ダニエルはジャーナリズム学科の3年生になったが相変わらずアリシアとの関係や予知能力は続いていた。今回予知したのはメキシコで起きる若者の不思議な死。大学教授が歴史の研究調査のためダニエルにメキシコ行きを提案したことから話の糸が絡まっていく。メキシコに着いたダニエルはまたもや不思議な出来事を体験する。それはアステカ文明の壮大なピラミッドの影に隠れて行われる先祖代々の黒儀式に関わることだった。
1771年のバルセロナ。17歳のコンスタンサは、アメリカ大陸の副王に仕えていた外交官の父の死後リマを後にし、長旅を経てバルセロナの祖父母のもとに身を寄せる。リマの風景や味やテクスチャーを記憶に刻み、唯一の遺品である料理帖を手に旅してきたのだった。料理帖はペルーの副王の料理人である、彼女の最初の師匠アントワーヌ・シャンペルの直伝だった。バルセロナに落ち着いたコンスタンサは偉大な料理人になることを夢見るが、女性である故に門は閉ざされている。
エリカがアイデンに出会った日、ふたりともほんの子どもだったが、エリカは言い知れぬ強い衝撃を感じて逃げだした。逃げる途中でエリカはドラゴンと出会い、それがもとで「ドラゴンの貴婦人」となる。その首に賞金がかかった、なぞに包まれた正義の旗手だ。
十代のスペイン人女性作家が書いた、愛とファンタジーの感動の物語。