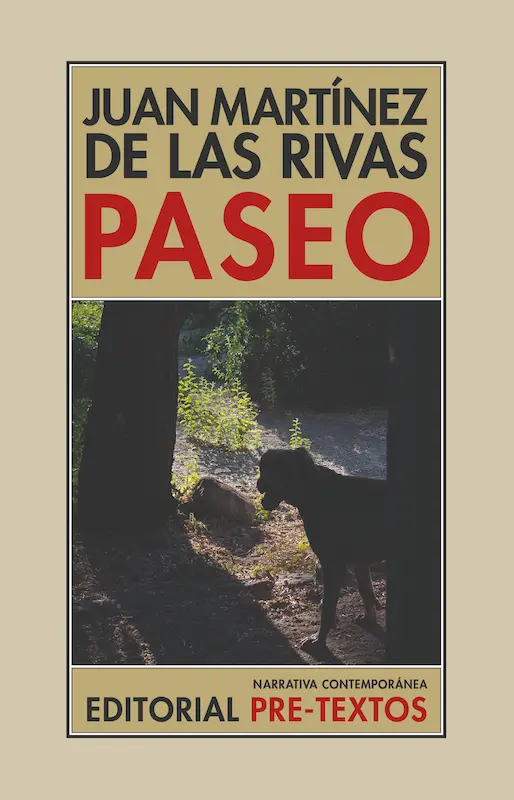
散歩
レポート執筆者:佐藤 晶子
Akiko Sato
■概要
医者であり作家である語り手が相続した庭園と、その庭園での庭仕事にまつわる考察・エッセイ・日誌・詩。
■あらすじ
医師として働く傍ら文学活動も行う「わたし」は、叔父のパコから庭園を相続したが、維持するための資金もないため、売却するつもりでいた。しかし、長年庭園の管理に携わってきた老庭師のマテオの願いにより、共に木々の世話をするうちに、自分で庭の管理を行うことに気持ちが傾いていった。当時「わたし」は33歳、それまでの住居や仕事を整理し、歴史ある街の城壁のすぐ外に位置するその「サン・セグンド庭園」に移り住んだ。庭仕事の経験などほとんどなかったため、最初は、マテオから庭仕事の手ほどきを受けた。マテオが引退すると、一人で試行錯誤しながら20年かけて、様々な作業や植栽、動物、庭園の設計などについて学びながら、荒れていた庭園を修復していった。
訪問してきたフランス人の庭園歴史家に触発されて参加した庭園建築講座では、自分の庭園の驚くべき由来が判明した。スペインで最も優れた庭園設計家と評されたハビエル・デ・ウィントゥイセンが、エウゼビ・グエイ(バルセロナのグエル公園などを設計したガウディのパトロンであったグエイの息子)の依頼で設計をした庭だったのだ。ウィントゥイセンは、当時の芸術・文化界では有名で、様々な文化人と交流があった人物であり、自身も画家としても成功した。依頼者グエイと交流しながら、共に庭園プロジェクトを推進していった様子がうかがわれる。しかし、完了後には庭園は放置され、「わたし」の大叔父がグエイから庭園を買った。庭園の門扉はパコ叔父がよその邸宅の廃棄物を据え付けたもので、そこだけ周りから浮いているルネサンス様式の門だ。庭園内には、ケルトの彫刻や、様々な樹木、柱、池、噴水、小道、道具小屋、風見鶏、ツタが這う壁などがある。庭園内にある小さな家は庭を眺めるために作られたもので、この地の気候に合った造りをしている。つまり、燦燦と照る太陽の熱を遮る小さい窓の家だ。また、門は昔ながらの手動開閉式だ。現代の便利な機能はないが、様々な時代を感じることができるこの家と庭園が好ましい。
庭仕事をしながら、地元の人々や、移住者、訪問客との触れ合いがある。たとえば、庭仕事に不慣れな若い女流詩人は、庭にあるツタの剪定に後ろめたさを感じている。家を建ててマドリードから移住してきた夫婦へは、庭づくりのアドバイスをした。友人の作家から依頼され高校の教師向けの庭園講座を行った。バラの絵を描く画家に会いに行き、バラに捧げられた詩を書いた作家たちを思い浮かべる。庭仕事を理解して書かれた詩はないため、女流詩人と共に、これらの作家向けの12講の植物講座を空想してみる。庭園には多くのプロ・アマの庭師が訪れるが、園内の案内をすることもあればしないときもある。街歩きに出れば、犬の餌を買い、古書店に行き、旧市街の居酒屋で食事をする。新聞記事の取材をする小説家や、敬愛するノーベル賞作家もこの庭園を訪れた。鳥の専門家を招いての鳴き声講座も行い、様々な鳴き声を聞き分ける楽しいレッスンを受けた。木の専門家を読んでの講義も受けた。学ぶ喜びを再発見すると同時に、古い松の木は伐採すべきという現実を突きつけられる。
1570年にアントン・ヴァン・デン・ヴィンガルデが描いた俯瞰図やフェデリコ・ガルシア・ロルカの散文を引用し、サン・フアン・デ・ラ・クルスが修道会の果樹園を散策する姿を想像しながら、歴史ある街の姿を描き出す。市による古い城壁の保護や補修が庭園にも関わってくる。庭園に接した壁の取り壊し工事に対して市当局や建設会社に対する訴訟を起こしたが敗訴した。古い城壁の上から庭に入り込む人工物、それは不埒な若者たちが投げ入れる空き瓶だったり、飛んでくるビニール袋だったりする。
近くの墓地が人であふれる死者の日には、昔飼っていた犬たちを思い出す。今飼っている犬を連れ、息子と共に山道に散歩に行く。そしてある犬の死にゆくさまを思い出した。また、医師として携わった仕事で、動物実験に使われる犬たちを見たことも思い出す。
庭師は、日々繰り返される作業を行いながら、庭園内を歩きまわる散歩者だ。草取り、剪定、水やり、種まき、植え付け、移植、害虫や害獣の駆除、植栽の把握、水路や池、灌漑設備などの水回りの管理。細部に目を向け、微妙な変化を見出す。その日常は心を落ち着かせる。庭のサイクルは自分のサイクルとなり、点検のための巡回をするたびに驚きがある。年を経た庭の松が荒天の後に根元から倒れてしまうのは「自然による剪定」だ。新たに植える木を選ぶ。日々の出来事や見たこと、感じたことをつづっていく。樹木に関する文学に思いを馳せる。瞑想について考察し、草むしりはすばらしい瞑想だと考える。庭とはなんだろう。この本を書くことで、「わたし」は庭と自然について熟考をする。山に行けば鳥たちを観察し、家に戻れば関連する本を楽しむ。風景を眺めて、以前読んだ本を思い出し思索にふける。ウィントゥイセンの設計したこの庭園を深く知るにつれ、この場所の精神を垣間見ることができ始めたと感じる。様々な作家たちの言葉を思い浮かべながら、庭を満喫する日々は続く。
■所感・評価
庭仕事への愛があふれた作品である。語り手が相続した庭は単なる「庭」ではなく、観光客や研究者が好んで訪れるような規模と歴史のある庭園だ。その庭を自らの手で管理しながら、文学的・哲学的な思索をつづっていく。実際の農作業を地道に重ねてきた語り手の庭仕事に関する考察は、単なる言葉を連ねただけのものではなく、実感を伴うものだ。作品中、詩が挿入されているが、つづられるのは、庭仕事の合間に見かけた風景への感想から、「剪定をする時期がきた」といった実作業に基づくメモで、まるで詩的な農業日誌だ。
この作品に登場する庭は、スペイン中部の街アビラに実在するサン・セグンド庭園だ。「城壁と聖人の町」の別称で知られるアビラは、ローマ時代にその起源を持ち、街の周囲には城壁が高くそびえている。この城壁が、庭園の借景のようになっている。庭園を相続した経緯、庭園の成り立ち、日々の作業それぞれの描写は時系列ではなく、草むしりという瞑想の合間に沸き上がってきたことを取りとめもなく書き留めたような印象だ。(前項の「あらすじ」では、関連のある内容ごとに整理してしまったのでご注意いただきたい。)また、スペインだけでなく、各国語の様々な書物の引用も多く、日本人作家の引用もあり(谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』と筒井康隆の『ポルノ惑星のサルモネラ人間』が引用されている)、著者の文学や書物に関する幅広い知識が散りばめられている。ただし、著者が池のコイを眺めながら思い起こした、米国大統領が訪日時に天皇陛下と共にコイに餌やりをしたエピソードは、実際には日本側は当時の首相が相手であったので、事実と異なることが記述されているのが気になった。
ちなみに、グエイ(グエル)から庭園を買ったという大叔父も、叔父も、著者本人も、スペインでは貴族(侯爵位)である。
由緒ある庭園の描写、文学的な思索、実際的な庭仕事の記録。読後は、まるで鳥のさえずりが聞こえる庭園の木陰を散策して瞑想をしたような充足感を感じられた。心を豊かにしてくれる一冊であるのは間違いないが、一方で、この本は読む人をかなり選ぶのではないかとも思う。例えば、引用されている作家は、スペイン語圏では文豪として知られていても、日本で広く知られているわけではないため、その作家が引用されている意味合いが読み手には見えてこないかもしれない。また、「アビラ」という街の名は作品中に一度も出てこない。街の描写から、スペイン人読者はあの街だ、と察するのだろうが、日本人にとっては検索作業を要する類のものだ(私自身も「アントン・ヴァン・デン・ヴィンガルデが描いた俯瞰図」をネットで調べて、アビラのことだと分かった)。庭仕事に関しては、私はたまたま地方在住で、つつましい庭を持つため、庭木の剪定や害獣・害虫、草むしりの話や、庭で騒ぐ鳥の声やら、飼い犬の話などは、ひどく共感できるものだった(さらに言えば、そんな由緒ある庭園に住みながら農作業をしているなんて羨ましい、とも思った)。しかし、スペイン文化好きの読者がこの本を手に取ったとして、庭仕事をしたことがない、あるいは興味がなければ、そういった描写は退屈に思えるのではないだろうか。レポートを書く立場の私にとっては「ドンピシャ」な内容の本だっただけに、客観的に判断するのが難しい。西洋文化好きでガーデニングに勤しみ読書を楽しむ余裕がある層向けとでもなるだろうか。
■試訳
(p.13の1行目から)
今日、庭師になって初めて、私は庭に出て、作業ではなく、何か書くことはないかと探した。それはこの本の書き出し部分になる。この本では、庭が庭師に教えてくれることを語りたいと考えている。ここ数日は、あまりやることがない。剪定や植え付けの時期はまだ来ておらず、水やりはもう必要ない。今は落ち葉や松の葉を拾わず、ただ溜まっていくのを見ているが、気にしないことにする。長年の経験から、春と夏の作業の後には、働く意欲を取り戻すことが大切だと学んだ。この辺りの気候では、秋の中頃から冬の中頃までが休息期となるが、放置したままの歩道や生垣、花壇を眺めているうちに、庭仕事をやる気がむくむくと起こってくるのだ。
何ヶ月も続いた干ばつの後、やっと雨が降った。夏の終わりの野原で、水のない小川沿いに、干からびながらも生き残った木々の間、乾いたポプラの老木が灰色に立ち枯れているのを見つけた。庭仕事は、自然を見る目を新たにさせる。子供の頃、私は木に登ったりその実を食べたりすること以外、植物には全く興味がなかった。また、若い頃にやったことがある庭仕事は、住人が旅行に出かけている間にアパートの植物に水をやる程度のもので、その仕事を引き受けたのは、植物が好きだからというわけではなく、他人の家をいつわりに所有する時間を楽しみたかったからだった。しかし、33歳の時から、私は(他に候補者がいなかったため)ある卓越した芸術的庭師の作品、つまり、親戚から予期せず相続した、繊細で複雑な庭園の世話をすることになった。最初の仕事は、害虫、樹木の病気、水漏れ(1メートル以上も水が真上に噴き出すことが何度もあった)、その他の庭の緊急事態に対処することや、屋根の崩壊を引き起こす恐れのある虫食いの梁や、住宅内の危険なほど老朽化した鉛の配管や電線を交換することだった。サラリーマンだった自分の場合は、維持管理が大変なこの邸宅を売却するのが理にかなっていただろう。しかし、この場所に無性に惹かれた私は、都会と仕事を離れてこの家に移り住み、庭園を少しずつ修復することした。20年かかった。最初の数年は、師であり友人でもあった老庭師がいてくれたが、彼が亡くなった後は、一人で植物の世話をし始めた。植物が新たな師となったのだ。
この庭の前の所有者たちは、一年のうち、花の咲く時期に訪れ、上流社会の人々を迎えてパーティーを開き、庭の隅々に貴重な芸術品を持ち込んだ。彼らは、自分の手で植えたり剪定したりしなかったし(それを行ったのは庭師たちで、時には同時に3人が雇われていた)、暖炉やストーブを準備したり、菜園や鶏小屋で採れた食材を使って料理を作ったりもしなかったし(それは料理人たちがやった)、庭に招待客用のテーブルを並べたりもしなかった。しかし、何よりも、一年を通して庭の営みに立ち会うということをしなかった。私は、ジャン・ジオノの著書『本当の豊かさ』の題名のとおり、その幸運に恵まれた。庭師になること、庭師であることは、長年にわたり私の特権となった。

