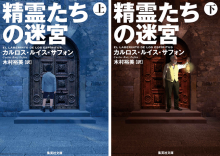
セルバンテスの次に世界で多く読まれている スペイン人作家といわれるカルロス・ルイ ス・サフォン。彼の『精霊たちの迷宮』の邦 訳が集英社文庫から出版された今年、翻訳出 版記念トークがインスティトゥト・セルバン テス東京で開催され、翻訳者の木村裕美氏、 バルセロナの著作権エージェントのアントニ ア・ケリガン氏、そしてサフォンの編集者 だったエミーリ・ロサーレス氏が、サフォン について語りました。
木村: カルロス・ルイス・サフォンは『風の 影』『天使のゲーム』『天国の囚人』という「忘れられた本の墓場」シリーズの最終 章『精霊たちの迷宮』を書き終えた4年後の 2020 年、残念なことに 55 歳で亡くなり ました。私は翻訳の草稿が終わらないときに逝去のニュースを聞いてショックを受け ましたが、彼が丸 15 年かけて書き上げたこの四部作に本当に命を懸けたんだなと、胸がいっぱいになりました。
この四部作は、霧がかかった幻想的でゴシック的なバルセロナを舞台に、センペーレ家の人々を中心としたミステリが繰り広げられる〝大河ロマン〟です。四部作は4つの扉で、どの扉から入ってもいいと著者は言っていました。どの扉から入っても大きな迷宮が広がっていて、ワクワクドキドキしながら読み進めると、その中で人物同士が次第に繋がっていきます。そして、最後にジグソーパズルのピースがすべてはまって、壮大な世界が見えるのです。一回読んで、ミステリのストーリーがわかった後でまた読み返すと、別のものや新しい細部が見えてきます。サフォンは言葉の魔術師です。読めば読むほど新しい発見があるというのがサフォンの作品の一番の魅力ではないでしょうか。
ケリガン:児童書の作家だったカルロスから、大人向けの小説を書いたから読んでほしいと原稿を渡されました。それは「忘れられた本の墓場」シリーズの一作目となる『風の影』でした。私はその作品をとても気に入り、出版も決まりましたが、当初スペインでの売れ行きはあまり芳しくありませんでしたね。ドイツの出版社が作品を気に入ってドイツ語版を出してくれたのですが、ドイツの外務大臣がテレビでこの作品を絶賛してくれて、それを機に世界的なブームとなりました。
実は当初、莫大な額の版権を伴った映画化の話がありました。その後、カルロス自身を監督に起用して映画化したいという提案もあり、元々映画に興味があったカルロスはかなり惹かれていたようでした。しかしある日彼は私のところにやってきて、「決めた、僕の作品は決して映像化しない」と言ったんです。「僕は本として読んでもらうために書いたのだから」ということでした。のちに私もその理由が理解できるようになりました。彼の作品では、言葉やシチュエーションのひとつひとつがとても 重要な意味を持っています。それを映像化すると、必ず原作を破壊することになってしまうでしょう。
カルロスは私のオフィスの近くに住んでいたので、よく立ち寄ってくれました。蘭の花がたくさんあって居心地がいいと言って、何時間もおしゃべりをしていきましたね。仕事のことだけではなく、私の知らない音楽家や作家について教えてくれました。彼がロンドンに行ってしまっても、私は時々会いに行っていましたし、彼の体調が悪くなってからも病状をメールで頻繁に知らせてもらっていました。残念ながら病に倒れてしまいましたが、彼の作品が死ぬことはないでしょう。特に『風の影』は100年後にも読み継がれている作品だと信じています。また、学校でも広く読まれているヤングアダルト向けの『Marina』も後世に残る作品ではないでしょうか。
ロサーレス:カルロスと私の最初の接点は実に最悪でした。彼がロサンゼルスにいるとは知らずに、夜中の3時に電話を掛けてしまったのです。就寝中にもかかわらず応答してくれましたが、平謝りして、改めて別の時間にかけ直しました。実際に最初にお会いした時も、私の狭い事務室にアントニアと一緒に来てくださったのですが、大きなカルロスの体は収まりきらず、ばつの悪い思いをしました。しかしそんな失敗にもかかわらず『風の影』で一緒に仕事をすることができ、出だしは思うように売れなかったものの、少しずつ海外にも読者が広がっていきました。
世界中の何百万人もの読者を夢中にさせただけでなく、これまで本を読まなかった人たちにも、読書の楽しさというものを教えたカルロスの作品に関わることができ、しかもこの天才的な著者と個人的な友情を築けたことをとても誇りに思っています。
彼の作品の素晴らしさとは、いったい何でしょうか? いまだに世界のネット上では、カルロスの作品に関するコメントが、毎時間4~5、場合によっては20くらい、さまざまな言語でアップされています。
私は、カルロスによって、「忘れられた本の墓場」という21世紀文学の最初の〝象徴〟が作られたと思っています。この本を読んだ世界各地の人たちが、実在しない秘密のこの図書館に共感しました。15~20年前、「文学や紙の書籍は今の状態で存続し得るだろうか」という疑問が沸き起こりました。実際の〝書籍〟が将来存続するかということだけでなく、本が与えてくれる私たちの〝記憶〟そして〝感受性〟の存続を危うんだのです。しかし、カルロスはこの「忘れられた本の墓場」で、私たちが読書を続けることを予言したのだと思います。
当初、カルロスの作品はジャンルについてもミステリ、ゴシック小説、成長物語、感傷小説など意見が分かれました。また類似の作家として、ボルヘスやエーコなどの名も挙げられました。確かにこれらの作家の影響もあるでしょうが、カルロスのスタイルは唯一だと思っています。『ドン・キホーテ』も当時流行していた騎士道小説と混同されましたが、実際は違います。騎士道小説の要素も確かに入っていますが、ジャンルとしてはまったく別のものです。それと同じことがカルロスの作品にも言えると思います。現代文学の面白いところを取り込んで、カルロスならではの作品として仕上げています。
子どもの頃から小説家になりたくて、コンクールに作品を送ったりしていたというカルロスは、今年発行されたスペインの切手「小説家シリーズ」の第一号の顔として選ばれました。もう一緒に食事をして文学談義をすることは叶いませんが、カルロスがスペイン文学の最高峰に立ったことを嬉しく思います。


