
スペインの子どもの本を翻訳するようになって25年ほどになる。翻訳する本を探そうという目的をもって初めてスペインで書店めぐりをしたのは1994年だったが、その頃は児童書コーナーの大部分をペーパーバックの読み物が占め、絵本はほんのわずかだった。1975年に独裁が終わって言論の自由を手に入れたスペインの1980年代は、独裁の言論統制下では出せなかった作品が、溢れるように生まれた熱気あふれる時代で、1990年代もまだその余韻が残っていた。空想的な冒険小説を得意とする『アドリア海の奇跡』(徳間書店)のジョアン・マヌエル・ジズベルトや、批判を込めて歴史に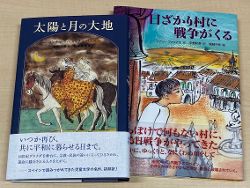 目を向けた『太陽と月の大地』(福音館書店)のコンチャ・ロペス=ナルバエス、市井の人びとを淡々と描いた『日ざかり村に戦争がくる』(福音館書店)のフアン・ファリアスなど、当時を代表する作家たちは、それぞれ個性的な物語世界を持っていたように思う。
目を向けた『太陽と月の大地』(福音館書店)のコンチャ・ロペス=ナルバエス、市井の人びとを淡々と描いた『日ざかり村に戦争がくる』(福音館書店)のフアン・ファリアスなど、当時を代表する作家たちは、それぞれ個性的な物語世界を持っていたように思う。
また、スペイン語以外のスペインの公用語カタルーニャ語、バスク語、ガリシア語の作品に、スペイン全国で目を向けられるようになったのも90年代だった。バスク児童文学研究家のシャビエル・エチャニスによると、バスクの児童文学がスペインの児童文学史の中で初めてとりあげられたのは1992年らしい。バスク語では、『アコーディオン弾きの息子』(新潮社)が翻訳出版されたベルナルド・アチャガが、児童文学を何点か発表して注目され、ガリシア語のアグスティン・フェルナンデス=パス、カタルーニャ語のエミリ・テシドールなどの作品がスペイン語に翻訳され、スペイン全体で読まれるようになった。
状況が大きく変わったのは2000年前後だろう。書籍編集のデジタル化とともに、「ブーム」と呼ばれるほど絵本が増え始めた。作り手も読み手も、絵本という媒体の魅力に目覚めたようだった。80〜90年代は絵本を知る編集者は少なく、形は絵本でも、挿絵つき読み物がほとんどだったのだが、1998年にはガリシア地方のポンテベドラで「絵本」に特化した小出版社カランドラカ社が誕生し、オリジナル作品を刊行すると同時に、それまでスペインでは知られてこなかったセンダックやローベルの絵本を紹介するようになった。また、『民主主義は誰のもの?』ほか全4巻の「あしたのための本」(あかね書房)の版元メディア・バカ社も1998年に「すべての読者のための絵のついた本」の出版社としてバレンシアで設立された。さらに2000年には、『むこう岸には』(ほるぷ出版)、『パパのところへ』(岩波書店)の版元であるベネズエラのエカレ社が、バルセロナに拠点をおくようになった。この頃から、絵とテクストが共に物語る、絵本らしい絵本が多くなった。
また、スペインの絵本の特徴として、ニュースパニッシュブックスで紹介され出版された絵本『マルコとパパ』(偕成社)や『エイハブ船長と白いクジラ』(ワールドライブラリー)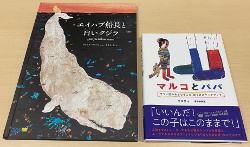 でもわかるように、大きさはこのくらい、ページは32で、というフォーマットにとらわれないことが挙げられる。また、テーマも表現も自由で、よいと思うものを噛み砕かず、子どもの読者にもそのまま投げるところがある。「こういうのもありか!」と、驚かされることがある。
でもわかるように、大きさはこのくらい、ページは32で、というフォーマットにとらわれないことが挙げられる。また、テーマも表現も自由で、よいと思うものを噛み砕かず、子どもの読者にもそのまま投げるところがある。「こういうのもありか!」と、驚かされることがある。
今年のニュースパニッシュブックスに参加したア・ブエン・パソ、ココ・ブックス、タカトゥカ、トゥーレ、ヌベオチョ、ブッコリア、フベントゥを含む、独立系の23の絵本出版社は、2018年には¡Âlbum!というグループを作った。書店でフェアを企画したり、ブックフェアに共同ブースを出したり販売面で協力しあいながら、本づくりでは切磋琢磨し刺激しあい、絵本出版を牽引している。
また、それ以外にも、『こんにちは! あたらしいいのち』(青山南訳 河出書房新社)のような、斬新な知識の絵本を次々出しているサオリ・デ・イデアス社、文学やグラフィックへの関心の強いフルヘンシオ・ピメンテル、リブレ・アルベドリオ、ノルディカ、個性派の画家のエレナ・オドリオソラが起こしたモデルナス・エル・エンブドなど、意欲的な絵本を出している出版社は挙げればきりがない。
版権取得の担当者が、「日本で売れそう」というものさしで見るのはわかるが、ニュースパニッシュブックスに来ている絵本を見るとき、規制の枠組みをちょっと脇に置いて、絵本の声に耳を傾けていただけたらと思う。
読み物に話を戻すと、2000年以降、「ハリー・ポッター」など、英米で話題の作品がいち早く翻訳されるようになり、『漂泊の王の伝説』(偕成社)のラウラ・ガジェゴ・ガルシアのように、独裁後の多様な作品を読んできた作家の活躍が目立ってきた。
ニュースパニッシュブックスから翻訳された『だいじょうぶ カバくん』(講談社)、『ぼくを燃やす炎』(サウザンブックス)のような単行本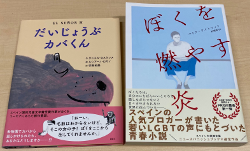 もあるが、絵を豊富にとりいれた小学校中学年、高学年向けくらいのシリーズものが多数出ている。スペインで一番人気はサッカーとミステリーが組み合わさったLos futbolísimos というシリーズ。現在17巻目が発売され、全部で100万部以上売り上げている。私自身は、こうしたシリーズもののエンタメに疎くよくわからないのだが、毎回ニュースパニッシュブックスでも多数紹介されている。日本や英米のこのような作品に詳しい方に、開拓してほしいところだ。
もあるが、絵を豊富にとりいれた小学校中学年、高学年向けくらいのシリーズものが多数出ている。スペインで一番人気はサッカーとミステリーが組み合わさったLos futbolísimos というシリーズ。現在17巻目が発売され、全部で100万部以上売り上げている。私自身は、こうしたシリーズもののエンタメに疎くよくわからないのだが、毎回ニュースパニッシュブックスでも多数紹介されている。日本や英米のこのような作品に詳しい方に、開拓してほしいところだ。
児童書の中で、最近、翻訳ものは数が減ってきていると言われるが、スペイン語の場合は、もともと減る余地がないほど少ない。国会図書館のOPACで数字を拾ってみると、国際子ども図書館に所蔵されている本で、刊行年が1999年、2009年、2019年のオリジナル言語が英語の本の冊数は532、803、690だが、スペイン語は7、10、10だ。市場原理から言って仕方がないのだろうが、それにしても少なく愕然とする。でも、前向きに考えるなら、まだまだ紹介されていない本はたくさんあるということだろう。
10年12回目を迎えるニュースパニッシュブックスでは、毎回全体の40%近くが子どもの本が占めるので、累積ではたぶん1000点以上が紹介されている。翻訳出版へのよい出会いが、さらに増えることを期待している。
宇野和美(うの・かずみ)
スペイン語翻訳者。東京外国語大学外国語学部スペイン語学科卒業。主な訳書に、エリアセル・カンシーノ『ベラスケスの十字の謎』(徳間書店)、ローレンス/マヨルガ『おにいちゃんとぼく』(光村教育図書)、イソール『ちっちゃいさん』(講談社)、マリア・ヘッセ『わたしはフリーダ・カーロ』(花伝社)など。東京外国語大学講師。イスパニカ通信添削講座で後進の指導にもあたる。翻訳のスピンオフで開いたスペイン語の児童書専門のネット書店、ミランフ洋書店は今年で13年になる。
日本でNew Spanish Booksのサイトを立ち上げて今年で10年目。1回目から、New Spanish Books全体の計画や運営に関わってくださっただけではなく、毎回スペインから届く全書籍の概要の翻訳・コーディネートもしてくださっている宇野和美さん。スペイン語圏の児童書を中心とした翻訳者としても第一線で活躍されています。そんな宇野さんが、スペインの児童書出版業界の全体像がよくわかるエッセイを寄稿くださいました。


