
エッセイ
小説と風景
海外小説の醍醐味は、その舞台となる地に旅できること、知らない土地でも、本のページをひらくだけで、文字の奏でる旋律に想像力が飛翔して、映画のシーンを観ているように小説の世界に誘いこまれてしまう。物語の行方をドキドキしながら追う楽しさはもちろん、そこには登場人物の歩いた道があり、広場があり、教会や建物やカフェ、海や山の自然の姿がある。どこにでもいそうな市井の人、彼らの日常、語り手の目に映る風景がそのまま目の裏にうかび、ページを飾る色彩や音、においや空気まで感じられるのだ。
これまで訳した作品の舞台はバルセロナが多かった。そして思えば、雨の風景が多かった。
灰色に降りつづく雨、湿った空気感は、スペインの強烈な夏の陽ざし、乾いた大地に巨人のごとき風車群が立ちならぶ“ラ・マンチャ”のイメージからは遠く思えるけれど、スペインの素顔はひとつではない。大西洋と深い緑のガリシアからバスク、地中海とピレネーに抱かれるカタルーニャ、曠野のカスティーリャから、光と影のアンダルシアまで無限の風景との出合いがそこにあり、私たちは思いのままに旅できる。
古代ローマの時代から中世、近代の王政から共和制と、歴史の重層をなすバルセロナは、フィクションの世界でも、その魅力を存分に発揮する

個性以上のパーソナリティーをもつ都(まち)としてバルセロナを描いたのは、カルメン・ラフォレットの名作『なにもない』(河出書房新社)。内戦直後の灰塵が髄までしみこんだ当時の風景に、18歳の主人公アンドレアの心象風景を重ねたラフォレットのバルセロナは、この小説のもうひとつの主役になり、奇妙な住人たちが住むアリバウ通りは一種のエンブレムとなった。

“海の聖母”を祀る教会を建てた“海の仲士(バスターシュ)”たちの汗と潮の香りがする『海のカテドラル』(RHブックス+プラス)は中世の激しい横顔を、銀板写真のセピア色の風景にガウディの極彩色の建築物が立ちあがる『ガウディの鍵』(集英社文庫)はファンタジックで謎にみちた時空を描いた。
『風の影』(集英社文庫)にはじまる4部作で、壮大なミステリーの小説世界を織りなすカルロス・ルイス・サフォンは、「忘れられた本の墓場」の迷宮をめぐる幻想と闇の都(まち)バルセロナを現出した。
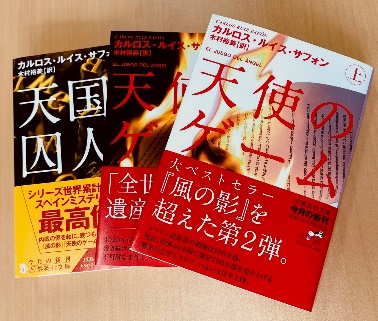 様々な小説の作中人物たちが、どこかで知らずに時を隔てて行き交っている、そう想像するのは楽しい。『海のカテドラル』で主人公のアルナウが信仰を捧げたサンタマリア・デル・マール教会は、『天使のゲーム』(集英社文庫)で魂を売った作家の書斎に鐘音を響かせ、『なにもない』のアンドレアは内戦の炎で黒ずんだ聖堂のステンドグラスに荒廃の詩情を見る。彼女が大きなトランクを抱えて到着するフランサ駅は別れと再会の場、『風の影』のフリアンはここでパリ行きの列車に乗り、『天国の囚人』(集英社文庫)のフェルミンは逃亡の果てにここに降り立った。フリアンが少年時代に通ったカルマ通りの図書館は、路面電車に轢かれた建築家ガウディが最期を迎えた元聖十字架救護院。そのガウディのグエル公園に隣接する館で、作家のマルティンは謎の編集人と契約をかわすことになる。
様々な小説の作中人物たちが、どこかで知らずに時を隔てて行き交っている、そう想像するのは楽しい。『海のカテドラル』で主人公のアルナウが信仰を捧げたサンタマリア・デル・マール教会は、『天使のゲーム』(集英社文庫)で魂を売った作家の書斎に鐘音を響かせ、『なにもない』のアンドレアは内戦の炎で黒ずんだ聖堂のステンドグラスに荒廃の詩情を見る。彼女が大きなトランクを抱えて到着するフランサ駅は別れと再会の場、『風の影』のフリアンはここでパリ行きの列車に乗り、『天国の囚人』(集英社文庫)のフェルミンは逃亡の果てにここに降り立った。フリアンが少年時代に通ったカルマ通りの図書館は、路面電車に轢かれた建築家ガウディが最期を迎えた元聖十字架救護院。そのガウディのグエル公園に隣接する館で、作家のマルティンは謎の編集人と契約をかわすことになる。
フィクションの産物であれ、地図を片手に小説の舞台をまわるうちに、作者の確かな足跡が感じられることがよくあった。「忘れられた本の墓場」があるはずのアルコ・デル・
 テアトロ通り、「センペーレと息子書店」のサンタアナ通り、「塔の館」のフラッサデース通り、ラバル地区の怪しげなノウ・デ・ラ・ランブラ通り… 記憶に刻まれた場所は数知れないけれど、かつて訪れたモンジュイックの南西墓地は中でも鮮烈な印象だった。サフォンの小説の舞台でなければ、まず行くこともない場所だ。市内からほぼ無人のバスに乗り「墓地の入り口で降りたい」と言うと、運転手と唯一の乗客の女性に怪訝な顔をされた。モンジュイックの丘に永遠にひろがる風景はまさに作者の筆どおり、天使像や十字架の林立する永遠の都市(まち)。坂道や階段をいくつも上がり、高台の木陰に着いたとき、周囲の景色が小説の描写に重なった。地中海を見おろす石垣つきの高台、飾りのない墓… 「そうか、ここなんだ!」愛すべき作中人物イサベッラの墓を見つけた気がした瞬間、そこはもはや地理上の一点でない、まったく物語の場面のとおり、墓地のうえにひろがる空が、海の青さに溶けていた。
テアトロ通り、「センペーレと息子書店」のサンタアナ通り、「塔の館」のフラッサデース通り、ラバル地区の怪しげなノウ・デ・ラ・ランブラ通り… 記憶に刻まれた場所は数知れないけれど、かつて訪れたモンジュイックの南西墓地は中でも鮮烈な印象だった。サフォンの小説の舞台でなければ、まず行くこともない場所だ。市内からほぼ無人のバスに乗り「墓地の入り口で降りたい」と言うと、運転手と唯一の乗客の女性に怪訝な顔をされた。モンジュイックの丘に永遠にひろがる風景はまさに作者の筆どおり、天使像や十字架の林立する永遠の都市(まち)。坂道や階段をいくつも上がり、高台の木陰に着いたとき、周囲の景色が小説の描写に重なった。地中海を見おろす石垣つきの高台、飾りのない墓… 「そうか、ここなんだ!」愛すべき作中人物イサベッラの墓を見つけた気がした瞬間、そこはもはや地理上の一点でない、まったく物語の場面のとおり、墓地のうえにひろがる空が、海の青さに溶けていた。
サフォンの最後の作品となったシリーズ完結編の『精霊たちの迷宮』(邦訳刊行予定)は、バルセロナとマドリードを結ぶ深遠なミステリーの旅。雨といえば、登場人物たちの暗い過去を映すかのように雨の日々の風景に彩られる。
フェルナンド・アラムブルの『祖国』(河出書房新社)も雨だった。こちらの舞台はバスク。映画に名場面があるように、小説にも忘れ得ないシーンがある。のちにテロの犠牲になる企業家のチャトと、武装集団ETAに身をおくホシェマリが雨のなかで向かいあい、その瞬間、教会の鐘が一時を打つ。ホシェマリは無言で立ち去り、チャトは家に向かった。その同じ午後、激しい雨のなかで、チャトは何者かに銃殺されるのだ。物語を紡ぐ2家族9人は全員がどこかの場面で雨にあっている。彼らの心模様のように降りつづく雨、でも雨はいつかやみ、そのあとには光がある。作者のアラムブルは複雑なバスクの素顔を真摯な筆で浮彫りにした。『祖国』の風景はいちど旅したら忘れられない。そしてその旅をくり返すことで、灰色の雨のむこうにあるバスクの比類ない色彩が見えてくる。海と山に抱かれた自然の色彩、豊かな食材、潮騒や風の音、民族楽器の奏でる音楽も、人々が太古から受け継いできたバスク語の響きも。
矛盾を抱えながらも多様性を誇りにするスペインの土壌から生まれた作品たち。人生に、時代に、歴史に翻弄される登場人物とともに、様々な土地の、様々な風景を歩きまわれる楽しさは比類ない。冒険の旅、ミステリーの旅、恋愛の旅、省察の旅… コロナの時代にあっても、本のページをひらくだけで、私たちはどれだけ素敵な旅ができることか。
木村 裕美(きむら・ひろみ)
上智大学外国語学部イスパニア語学科卒。1991年よりマドリード在住。
主な訳書に、カルメン・ラフォレット『なにもない』、カルロス・ルイス・サフォン『風の影』、イサベル・アジェンデ『日本人の恋びと』、アルトゥーロ・ペレス・レベルテ『戦場の画家』、フェルナンド・アラムブル『祖国』ほか。
『風の影』シリーズが日本でも話題になったカルロス・ルイス・サフォンや、今年4月に邦訳版『祖国』が出版されたフェルナンド・アランブルなど、世界的ベストセラーのスペイン小説を数多く日本語で紹介してこられた、スペイン語翻訳者の木村裕美さん。コロナ禍で旅行ができない今こそ、小説の中で海外の空気を感じる醍醐味について、エッセイをお寄せいただきました。


