エッセイ
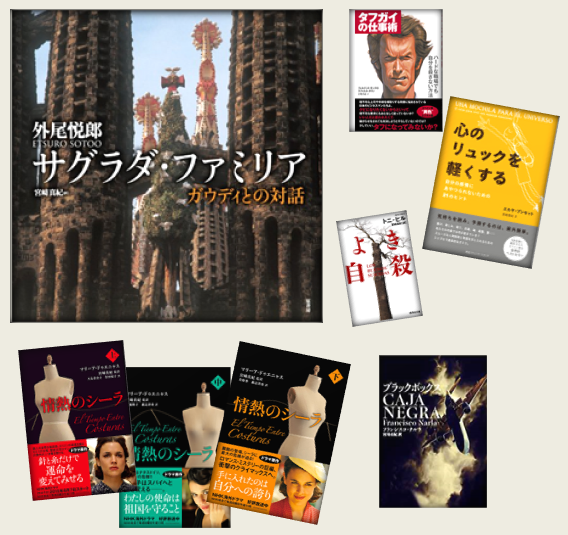
スペイン語そして英語の書籍翻訳を多数手がけてきた宮崎真紀さん。当ニュー・スパニッシュ・ブックスでご紹介してきた本の中からもたくさん翻訳して日本の読者に届けてくださっています(写真)。また当サイトの「日本向けおすすめ書籍」にノミネートされる本を読みレポートを書くリーダーとしても、ほぼ毎回ご協力いただいています。特にエンタメ系に詳しい宮崎さんに、海外ミステリをおもしろい視点から論じていただきました。
独裁政権下ではミステリは成立しないのか?

《探偵小説は市民社会の産物だと言われている。ポー、コナン・ドイル以来、探偵小説は、イギリスやアメリカに栄えている。フランスやドイツにも、何人かの有能な作家が登場したが、探偵小説の本流から見れば、あくまで傍流にすぎない。また、ロシヤとか中国などのような独裁国や遅れた社会には、ほとんど根をおろさなかった。つまり、探偵小説は、アングロ・サクソン民族とともに栄えた、一小説形式である。そして、この現象は、イギリスやアメリカが、民主主義のもっとも進んだ国であったという点から発しているのだ。いや、探偵小説は、民主主義を前提にしているとさえ言える……独裁国には迷宮入りの事件も、誤判の事件も、珍しくない。犯人がかならず逮捕されるという習慣は存在しない。》──江戸川乱歩、松本清張・共編『推理小説作法』(光文社文庫)所収「推理小説のエチケット」(荒正人)より
こんなふうに、ミステリが成立するには民主主義社会であることが基本条件だというミステリ・デモクラシー説というのがある。なるほど、司法や法執行機関が独裁者や体制の思いのままに動く社会では、客観的な証拠や合理的な推理が意味を成さなくなるのは確かだろう。当たり前のように出版物の検閲がおこなわれ、自由な出版活動ができないということもある。たとえばフランコ政権下のスペインでは、英米に対して〝犯罪そのもののない社会〟であることをアピールするため、犯罪小説はほとんど書かれなかった。そもそも、ミステリを含めエンターテインメントというのは、読者を楽しませることを目的とした、市場を意識したジャンルなのである。その意味で、市場そのものがない社会では発展しづらいだろう。
でも本当に? 独裁政権下の社会を舞台にしたミステリは成立しないのか? R・リーバス&S・ホフマン『偽りの書簡』(原題:Don de Lenguas)は、まさにフランコ独裁政権下の1950年代のバルセロナで、新米新聞記者アナと文献学者ベアトリズが富豪未亡人の殺人事件とその背後に潜む陰謀に挑むミステリである。何かと抑圧され、思うように力を発揮できないなか、ふたりの女性が小市民なりに知恵を絞る姿に胸が熱くなり、巨悪に対して一矢報いる結末に胸がすく(ちょっと苦味も残るのだが)。この小説はむしろ、こういうさまざまな制限がある時代だからこそ、それに立ち向かう主人公たちの活躍が鮮やかに描けたと言えるだろう。
また、英国推理作家協会がその年の最優秀翻訳ミステリにあたえるインターナショナル・ダガー賞の一次候補にも選ばれた(2011年)、アルゼンチンのミステリ作家エルネスト・マジョErnesto Malloの『La Aguja en el Pajar(藁の中の針)』では、1970年代アルゼンチンの軍事独裁政権時代が舞台で、軍部や警察が何万人もの市民を弾圧した〝汚い戦争〟の真っただ中の社会が描かれている。引退間近のラスカノ警視が、体制側の拷問によって殺された複数の遺体のなかに紛れ込んでいた、〝別の理由による殺人〟の遺体を発見し、捜査を始める。同じ遺体ながら、体制側によって殺害された人々については事件視されないという不条理さが、軍事政権下の社会がいかに異様だったかを浮き彫りにしており、こういう時代背景でしか成立しえなかった快作だ。老警視と、亡妻とよく似た若きレジスタンス女性との淡い恋も絡み、彼が体制側に追われるようになるに及んで、物語はいよいよ面白くなるのだが……それはまたいつか別の機会に。
どうだろう、むしろ非民主的社会体制は、ミステリに必要な〝制限条件〟をあたえてくれる、ある意味すぐれた舞台装置と言えるのでは? ただし、民主主義的ミステリが合理性をもとにしているとすれば、こちらはいやでも非合理や不条理がつきまとう。そういう部分に違和感を覚える読者もいるかもしれないが、私からすると、欧米ミステリの文法からずれてぐらりと足元が揺らぐところこそが魅力だと思うのだ。
最初に引用した論説は半世紀以上前のもので、時代がかっているし、今ではフランスやドイツはもちろん、北欧などのミステリは国際的にも高い評価を得て、確固たる基盤を築いている。スペインやスペイン語圏のミステリおよびエンターテインメント小説が、独裁政権や軍事政権のせいでスタートが出遅れてしまったのは事実だろう。なにしろ、1970年代、80年代になってはじめて、民主化が導入されたのだから。
ミステリというジャンルそのものの確立もごく最近のことで、いわゆる文学との境界は曖昧であり、たとえば世界的ベストセラーとなったカルロス・ルイス・サフォン『風の影』は、スペイン国内ではミステリという認識はない。数年前に来日したスペイン・ミステリ作家の第一人者、ロレンソ・シルバ氏が来日講演で「スウェーデンの《ミレニアム》シリーズがスペインでも大ブレークしたことで、スペイン・ミステリが一気に活気づいた」と話していたのが印象的だった。《ミレニアム》シリーズがスペインで発売されたのは2007年だから、それぐらい最近のことなのだ。
「1960年代のラテンアメリカ文学ブームは、作家たちが海外に出てユニバーサルな言葉を得たことがひとつの原因だった」と翻訳家の木村榮一先生はおっしゃっていたが、スペイン語圏ミステリも、英米ミステリの模倣を重ね、ユニバーサルな言葉を得て、それが特異な魅力や地域性と結びついたとき、大爆発しそうな気がするのだ。いや、もうどこかで起きつつあるかもしれない。そして、それを翻訳できる日が楽しみでならない。
宮﨑 真紀(みやざき まき)
スペイン語圏文学・英米文学翻訳家。東京外国語大学外国語学部スペイン語学科卒。おもな訳書にヨブレギャット『ヴェサリウスの秘密』(集英社)、マラホビッチ『ブエノスアイレスに消えた』、パルマ『時の地図』(早川書房)、リーバス&ホフマン『偽りの書簡』(東京創元社)、『マラドーナ独白』(東洋館出版社)、ビアード『SPQR ローマ帝国史』(亜紀書房)など。


