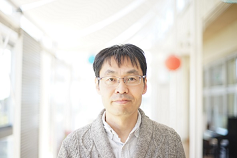
文学の赦し――ロベルト・ボラーニョの小説
僕にとって、ロベルト・ボラーニョとの出会いは衝撃だった。それまで中南米文学だと思い込んできたもの、すべてと違っていたからだ。確かに、ボルヘス『砂の本』の奇妙で凝縮された世界を愛していたし、ガルシア=マルケス『エレンディラ』の、傷ついたおっちょこちょいの天使の話も大好きだった。コルタサルの短編は不思議でスタイリッシュだったし、バルガス=リョサ『密林の語り部』では、一緒にペルーの川を遡っているみたいで興奮した。でも、ボラーニョは全然違う。
何というか、ボラーニョは、かっこ悪くて、都会的で、哀しくて、まるで自分や、昔の仲間の姿を見ているようだった。言いかえれば、文学にとてつもなく魅せられてしまって、自分も詩人になれるんじゃないか、あるいは小説家になれるんじゃないかと思いつめて、でも全然作品を書くことができず、仲間で集まって酒ばっかり飲んでいる感じ、と言えばいいのか。そこには中南米文学に付きものの派手な神秘的描写なんてない。ただただ、ダメな自分と地続きで、だからボラーニョの書く文章の中に、友達を見つけたみたいだった。そう、僕にとってボラーニョは、中南米文学で初めて見つけた友達だ。
こういう感覚は、J・D・サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』にも近い。クラスの仲間が何かについて論じている、でも話が逸れていってしまう。みんなはそれじゃいけないと言うけれど、むしろ脱線のほうに面白味があるんじゃないの、と主人公のホールデン・コールフィールドが言うとき、そうそう、その通り、僕もそう思っていた、と何度読んでも感じる。この、心の中にあるもやっとした感じをしっかりと言葉に表わしてくれたときの気持ちよさと、ホッとするような嬉しいような感じが、僕が好きな作家の条件だ。
ボラーニョに話を戻そう。彼の作品に出て来る人々は、ただダメなわけではない。むしろ、かつてダメだった人たち、というべきか。たとえばボラーニョ自身、売れない自称詩人として長い時を過ごしながらチリ、メキシコ、スペインと移動していく。そして1990年に息子が生まれたのを機に小説に転じ、突然大きな成功を収める。そして2003年に50歳で亡くなるまで、ほんの十数年の間に、世界的な作家にまで成るわけだ。ということは、書いているボラーニョはダメではない。極端に面白い作品を次々に発表する。売れっ子の書き手なわけだから。でも、作品に出て来る過去のボラーニョやその周辺の人々はものすごくダメだ。そしてボラーニョが書いている今、ましてや読者が読んでいる現在において、もう登場人物達はどこにもいない。というか、作品の中だけにいる。そう、青春まっただ中の彼らは消えてしまったのだ。だからボラーニョの作品は青春の死を悼むものとなる。
これは、『ノルウェイの森』など一連の村上春樹作品と構造的に同じだ。確かにかつて愛はあった。しかしその愛は最初から損なわれていて、主人公の努力にかかわらず、結局は女性の死とともに永久に消え去ってしまった。だからこそ、それを取り戻すために、主人公は神秘に頼る。井戸の底に降り、異界に入り込んで、死者と再会し、彼らと自分の魂を癒やして地上に戻ってくる。冥界譚となっている点では、ほとんど能と同じだ。
それではボラーニョ作品に神秘が存在しないのかといえば、実は明確にある。たとえば、ドイツ人の青年がカタルーニャの浜辺でひたすらウォーゲームをするだけの『第三帝国』で、ホテルの鏡を見た主人公は、自分の姿が映っていないのに気づく。ならばもう自分は死んでいるのか。あるいは、このホテルの中は外の世界とは違う、もう一つの現実なのか。その答えは明かされない。
あるいは『売女の人殺し』所収の「帰還」という短編にはこんな一節が出てくる。「死ぬと現実世界がほんの少しずれる、そのせいで目まいがする。いきなり度の合わない眼鏡を、元のとあまり違わないが別の眼鏡をかけたみたいな感じだ。何と言っても最悪なのは、選んだのが元の自分の眼鏡であって他人の眼鏡ではないと分かっていることだ。そして、現実世界がほんの少し右に、ほんの少し下にずれて、対象との距離が見た目には分からないほど微妙に変化し、その変化がまるで深淵のように感じられて、その深淵にまた目まいがするのだが、それはどうでもいいことだ」(141ページ)。世界がほんの少しずれて見え、そのずれの向こうに深淵が顔を出す。これこそがボラーニョにとっての小説の定義で、したがって彼の小説のことごとくが、死に取り憑かれている。
そのことがよくわかるのが『はるかな星』だ。なにしろ、主人公はビーダーという元仲間の暗殺に加担しようとしているのだから。なぜ、彼はビーダーを殺さなければならないのか。それはビーダーが文学愛好者に偽装した政府のスパイであり、主人公が愛した女たちを謀殺したからだ。アジェンデ政権のチリで、主人公は詩のサークルに属している。姉と妹でそっくりなガルメンディア姉妹と、ルイス=タグレも一緒だ。だがピノチェトのクーデターが起こったとたん、ルイス=タグレは本性を表わす。ビーダーと名を変え、わざわざ写真を撮りながらガルメンディア姉妹を殺す。後にご丁寧にもその写真展まで開く。
一方、主人公はピノチェト政権に捕まり刑務所にいる。そして他の囚人たちと一緒に空を見上げている。「それまで僕は、これほど大きな悲しみがひとつになっているのを見たことがなかった」(36ページ)。なぜか。ビーダーが操縦する飛行機が、飛行機雲を使って自分の殺した女たちの名前を空に書き込んでいたからだ。何のために。彼にとってそれはファシストの詩であり、同時に死者たちへの呼びかけの声でもあったからである。もちろん主人公はビーダーを深く憎む。彼こそが主人公の青春を殺し、愛する人を殺し、チリでの日々を殺した張本人なのだから。だが同時に、そこまで邪悪なビーダーを主人公は詩人として認め続ける。「それにもかかわらず、彼の作品は生き続け、(彼がおそらく望んだように)必死になって、それでも生き続ける」(116ページ)。ここがボラーニョの面白いところだ。
詩人たちは政治的な立場を巡って対立し得る。そして極端な場合には殺し合う。それでも、ボラーニョは彼らの中にある詩の魂を信じることを止めない。そうでなければ、『アメリカ大陸のナチ文学』なんて奇妙な作品を書くわけがない。収録された数多くの伝記に出てくる書き手たちには共通点がある。人種差別や同性愛者差別などを信じるファシストたちなのだ。だが、ボラーニョは一方的に彼らを非難はしない。むしろ文学を愛し、愛に破れ、傷つき、死んでいく彼らの哀れさを辿り続ける。
ならばボラーニョはファシズムを許容しているのか。かつてピノチェトに国を追われた彼がそうであるはずがない。むしろ彼は、人間であることの悲しみにまで降りていくことで、批判の向こう側まで突き抜けようとしていたのではないか。どんな人間も、どんな政治思想を抱こうとも、苦しみ、傷つき、死んでいく。他者に究極的に不寛容である彼らをも、命として抱き留めることで、寛容さの持つ力をボラーニョは示そうとしていたのではないか。まるでイエス・キリストのように。
彼にとって文学とはそうした大きな愛であり、そして詩人という、社会で最も弱い者たちの持つたぐい希な強さだった。だから、ボラーニョの作品を読みながら僕らはダメなまま赦されるのだ。
都甲幸治(とこう・こうじ)
1969年福岡生まれ。 アメリカ文学研究者、早稲田大学文学学術院教授。著書に『今を生きる人のための世界文学案内』(立東舎)、『21世紀の世界文学30冊を読む』(新潮社)、訳書にジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(共訳、新潮社)、『わたしの島をさがして』(汐文社)、チャールズ・ブコウスキー『勝手に生きろ!』(河出文庫)、ジャクリーン・ウッドソン『みんなとちがうきみだけど』(汐文社)などがある。読売新聞(2010-2011)、朝日新聞(2018-)書評委員。
スペインの全人口よりも多い5000万人以上のヒスパニック系が暮らす米国では、その文学にもヒスパニック系の影響が色濃くみられるようになってきました。英語にスペイン語をたくさん散りばめた文体で話題となった小説『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(ジュノ・ディアス著)の翻訳も手掛けた都甲幸治先生に、スペイン語圏文学について寄稿をお願いしたところ、迷わず選んだテーマはロベルト・ボラーニョ(1953-2003年)。そのダメ男ぶりに親近感を感じるそうですが…。近年日本でも次々と邦訳が出ている、50歳で早逝したチリ人作家の魅力について語っていただきました。


