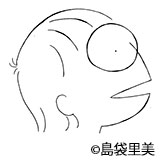
ポップな現代アメリカ文学を次々と翻訳し、日本における翻訳文学のカルチャーを大きく変えた翻訳家の柴田元幸氏が、アメリカ文学からみたスペイン語圏文学について語ってくださいました。
文学における自由不自由
何年か前に、イランのモフセン・マフマルバフ監督の『パンと植木鉢』(1996)を観ていて、ああやっぱり僕はハリウッド映画以外が好きなのだなあ、と思ったことがある。
――と、ハリウッド映画がぜんぶ同じ、みたいな何とも乱暴な書き方だが、まあそういう乱暴な話だということでお読みいただきたい。
『パンと植木鉢』は映画を作ることについての映画だが、ある場面で、主演俳優が「こんな映画は作れん」と怒って撮影所から出ていってしまう。残された監督やスタッフは、俳優が撮影所の門を出て、道を歩いていく後ろ姿を見ている。やがて誰かが、「あいつ、あそこの木まで行ったら、戻ってくるぜ」と言う。
俳優は歩きつづける。なおも数秒歩く。息を呑んで、というのともちょっと違う中途半端な緊迫感とともにわれわれはそれを見守る。そして俳優は、問題の木にたどり着き――
――そのまま歩きつづける。
これが、いいのである。
これが、僕によって乱暴に「ハリウッド映画」と十把一絡げにされた映画だったら、絶対にここで戻ってくる。少なくとも、その木に達したところで何かドラマが起きる。
そうした暗黙の約束事は、時にとても窮屈に感じられる。だから、そういう約束事から自由なものを見ると、それだけで、さわやかになる。
これまた乱暴な話をすると、文学というのはどちらかというと、約束事を強化するよりは、約束事を疑わせたり、じゅうぶん意識化されていない約束事を――なるべくならよい物語を通して――意識化・言語化したりする営みであってほしい。
だから、いろんな約束事から文学は自由であってほしいのだが、これがかならずしもそうは行かない。僕はいちおう北アメリカの文学にかかわっているのでこれを例にとると、1980年代から90年代あたりの北米では、少なくとも短篇小説はリアリズム一辺倒で、英語圏で最大の文芸誌『グランタ』が行なった北米新人作家特集に載った20本すべてがリアリズムの枠内に収まる作品だった、などということもあった(いまは幸いもっと多様)。
それから、これはむしろ矜持を感じさせるのだが、アメリカの女性作家の作品を読んでいると、日本の女性作家の作品でときどき見かける、包容力のあるお兄さん的な、少し離れたところから女性を包んでくれるような男性はまず出てこない。フェミニズム的思考の浸透が、そういう願望的思考を禁じているのだろうか。間違っても、そういう男性が日本には存在してアメリカには存在しないことではないと思う。人間の「性格」も関係の産物だから、同じ人物でも、日本の文脈内に置かれたのとアメリカの文脈に置かれたのとでは違う性格に見えてしまうということか。
いずれにせよ、そうしたもろもろの不自由さは、違う地域・言語の文学を読むことで見えやすくなったりする。たとえば、きわめて即物的に、長さの問題。アルゼンチンの作家セサル・アイラの作品は、邦訳・英訳を見るかぎり百ページ前後の中篇小説が多いようである。僕が知っているのは、邦訳『わたしの物語』(柳原孝敦訳、原題Cómo me hice monja, 1993)、英訳An Episode in the Life of a Landscape Painter(原題Un episodio en la vida del pintor viajero, 2000), Ghosts(原題Los fantasmas, 1990)の三冊だが、みな設定も展開も独特で、奇妙な緊迫感があり、長さが内容にぴったり合っているように思える。北アメリカで中篇に秀でた人というと、個人的にはスティーヴン・ミルハウザーとイーサン・ケイニンがすぐ思いつくが、彼らの場合はひとつの作品世界なりひとりの人物なりの細部を律儀かつ丹念に書き込むという職人的姿勢が中篇という長さを要請している気がする。アイラの場合、それとはだいぶ違う。
それで、いつも思うのだが、このように中篇で勝負する作家というのは、北アメリカでは商業的になかなか難しいのではないかと思う(ちなみにミルハウザー、ケイニンは「普通」の長さの短篇・長篇も書く)。アイラの英訳は、良質の外国文学を数多く出しているNew Directionsから出ているが、これはスペイン語の原作があるから本として出るのであって、もしこれが英語で書かれていたら、百ページ前後の小説が一冊の本として出るのは、かなり困難ではないかと思う。まずは雑誌掲載、というには少し長すぎるし、さりとて一冊の本として自立するには、(北アメリカの文脈では)少し短い。まさしく帯に短し、たすきに長し。アルゼンチンでも実はアイラ以外はけっこう大変なのかもしれないが、それでもやはり、こういう長さ、英米小説よりラテンアメリカ小説で多く見かける気がする。
逆に、長いものについて。長いもので最近の話題作といえば、むろんロベルト・ボラーニョの遺作『2666』(2004)である。今年、邦訳が出たが(野谷文昭、内田兆史、久野量一訳、白水社刊)、880ページ、6930円の大部にもかかわらず即増刷と聞いた。めでたしめでたし。
長さ・量に関連して圧倒されるのは、なんといっても、五部から成るこの長大な小説のなかでも一番長い第四部「犯罪の部」である。ある町で次々に起きる猟奇的な連続女性殺人事件が、ひとつずつ執拗に描写されていく。むろんそこにストーリーのようなものも絡むのだが、頭に(というか体に)残るのは、数々の事件をめぐる圧倒的な量の報告的記述である。量が質に転化する、というのはよくある話だが、これはそのきわめて異様な一例である。まだ一回通読しただけなので、これが全体にどう寄与しているかをきちんと言語化することはできないのだが(訳者の一人野谷文昭さんは、ゲラを読み返すたびに発見があって至福の時間だったと言っていた)、とにかく、読み進めるうちに、「なぜこんなに、似たような事件についてくり返し書くんだろう」という疑問が、まさにこのくり返しこそポイントなのかもしれないという思いに転じていく。類似の例としては、やはり連続猟奇殺人を題材にしたブレット・イーストン・エリスの『アメリカン・サイコ』の執拗な描写が思いつくが、『2666』は規模において上を行っている。
それで、これも、ボラーニョという名の通った作家であるがゆえに本国チリでも刊行可能になったのかもしれないが、かりにこれが北アメリカの、英語で書かれた作品だったら、編集者はこの長さを擁護するだろうか。それとも、商品として通用しやすいよう、短くすることを作者に要求するだろうか。作家の知名度、編集者の度量、出版社の財力、等々いろんな要素が絡むだろうから簡単には決められないが、とにかくやすやすと出版できるものでないことだけは確かだろう。
こうやってみると、少なくとも長さに関しては、なんだかラテンアメリカ文学がすごく自由に見えて、羨ましくなる。まあもちろん、一歩中に入ってみれば、また別の不自由があるのだろうけど。
話は変わるが、アメリカ合衆国の読者はアメリカの外の作品に目を向けようとしない、とはアメリカ内外でよく言われることだが、まあ比率的にはそうかもしれないけれど、こつこつ良質の外国文学を訳しつづける翻訳者・出版社が存在することもまた確かである。オルハン・パムク(トルコ)もミロラド・パヴィチ(旧ユーゴ)もW・G・ゼーバルト(ドイツ)も、僕はみなアメリカから出版された英訳を通して知った。アイラ、ボラーニョに関しても最初に知ったのは英訳。ただし、フリオ・リャマサーレス(スペイン)は、木村榮一訳・ヴィレッジブックス刊の邦訳『黄色い雨』を通して知ったし、邦訳はすでに三冊出ているが英訳は『黄色い雨』(日本とほぼ同時2004年刊)一冊のみ。しかも木村さんは、出版の見通しもないまま『黄色い雨』をこつこつ訳されていたのである(そして、そうやって訳していたのは『黄色い雨』一冊ではないことを僕は知っている)。こういう立派な行ないを一度くらいやってみたいものだが、北アメリカの商業主義にどっぷり浸かってしまっていて、まだ実行できていない。
柴田元幸(しばた・もとゆき)
1954年生まれ、東大文学部教授。アメリカ文学専攻。『生半可な學者』で講談社エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。ポール・オースター『幻影の書』、スティーヴン・ミルハウザー『ナイフ投げ師』、スチュアート・ダイベック『シカゴ育ち』など現代アメリカ文学の翻訳多数。著書に『ケンブリッジ・サーカス』など。


