Japan Panel's Choice
日本向けおすすめ書籍
日本市場向けに専門家が選んだスペインの新刊書籍をご案内します。
今回は以下の専門家の方々に選んでいただきました。 (以下あいうえお順/敬称略)
倉畑雄太(作品社)/松岡希代子・高木佳子・村内みれい(板橋区立美術館)/柳原孝敦(スペイン語圏文学研究、東京大学教授)/山本知子(リベル)
今回は以下の専門家の方々に選んでいただきました。
野谷文昭 (選考委員長:東京大学名誉教授) (以下あいうえお順/敬称略)
今回は以下の専門家の方々に選んでいただきました。
野谷文昭 (選考委員長:東京大学名誉教授) (以下あいうえお順/敬称略)
各書籍のレポートを担当したのは以下の方々です。(あいうえお順/敬称略 第一次選考で選ばれた16作品のレポート作成者)
今木照美/上野貴彦/宇野和美/國貞草兵/小机菜穂/佐藤晶子/嶋田真美/高木菜々/長神未央子/中山 映/藤井健太朗/村岡直子/横田佐知子/吉田 恵/和田優子
今回は以下の専門家の方々に選んでいただきました。
野谷文昭 (選考委員長:東京大学名誉教授) (以下あいうえお順/敬称略)
今回は以下の専門家の方々に選んでいただきました。
野谷文昭 (選考委員長:東京大学名誉教授) (以下あいうえお順/敬称略)
文学
『La casa limón(レモンハウス)』は、寓話に近い示唆的なトーンで、ルーマニアにおけるチャウシェスク政権の崩壊の年月を少女の無垢な目を通して描く。共産主義の終焉を生きる少女は、家族が直面する個人的な災難とトランシルヴァニア出身の祖父母が持つ古くからの伝統の間で、周囲で何が起こっているのかを理解しようとする。ダイニングテーブルの下に身を隠し、本の城に囲まれて、少女は、自分が期せずして父親の奇妙な病気を引き起こしてしまったのではないかと心配する。規制と悪名高いセクリターテへの密告が続く中、彼らは独裁政権の終焉が近づいていることを知らない。正確で、生々しいが夢のような筆致で描かれた、リリカルで感動的な小説。少女の声と全体主義の影が私たちに問いかける普遍的な物語。
詳しく見る

文学
NEW
レモンハウス
La casa limón
コリナ・オプロアエ
Corina Oproae
Tusquets Editores
すでに老境に入った二人の姉妹が、青春時代のお気に入りの映画を演じて遊ぶ。二人のティーンエイジャーが終業式の日に、これまでとは異なる視線で生々しく互いを発見する。ある女性が、彼女の人生を永遠に変えたパーティーを回想する。イタリアのある都市で、ひとりの男が大聖堂の建設現場に入り込み、予期せぬ結果をもたらす指令を受ける。巧みな心理描写と日常の微妙な混乱を用いて、説明不可能なもの、震撼とさせるもの、語られないもの、予期せぬ形で私たちを変え、決して忘れられなくなるものを浮き彫りにした短編集。
詳しく見る

文学
NEW
見えないもの
Lo que no se ve
クリスティーナ・フェルナンデス=クバス
Cristina Fernández Cubas
Casanovas & Lynch Literary Agency
プエブロ・チコは、時に霧に包まれ、雪に覆われる山間の小さな村だ。時に動物が迷い込み、人が姿を消すこともある山中にある。一見穏やかな場所で、今は数少ない寡黙な老人たちが住んでいる。その静けさに、秘密や暴力的な過去、復讐の念が隠れているとは、誰も思わない。1年間そこで過ごそうと都会からやってきた夫婦も何も疑っていない。しかし、父親がそこで生まれたという理由でそこに来ることを選んだアリアドナはやがて、山に何かが隠されていると感じ始める。村の住人たち、特に透き通るような目をして幻覚にも似た謎めいた言葉を話すペドロと出会い、アリアドナは父親が自身の過去についてなぜ何も語らなかったのかをようやく理解するようになる。それは、村全体が目を閉じ、見ないことにしようと決めた過去だった。 読者を巻き込むざらついた文体で書かれたこのポリフォニックな小説で、エドゥルネ・ポルテラはある村、ひいてはある国家、大陸、そして人類の集団的記憶を鋭く問いただす。
詳しく見る

文学
NEW
閉ざした目
Los ojos cerrados
エドゥルネ・ポルテラ
Edurne Portela
Galaxia Gutenberg SL
植物について何も知らない作家が、何年も手入れされずに放置されていた庭と家の世話を予期せずして引き受けることになる。引退間近の庭師が、彼に最初の手ほどきをする。その庭師が引退した後、作家はひとりで庭の手入れをし発見を続ける。本書は、庭を言葉で再現することを目的とする。生き物、植物、地元の人々との出会いの物語や、時の移ろいの観察を通して、いかにして彼が庭師となり、彼が手入れし創造する世界の断片がいかに生きていくかが綴られる。自然への研ぎ澄まされた視線を備えた文章は、訪れる人にその場所の秘密を教える散歩のようだ。
詳しく見る
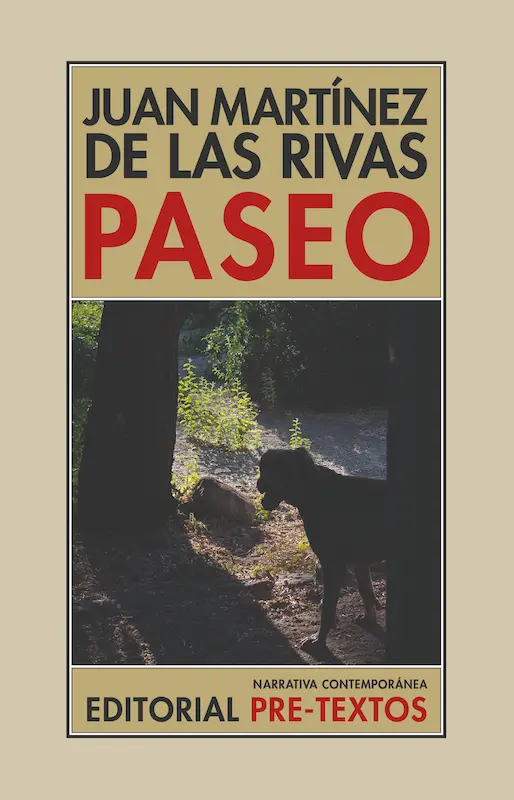
文学
NEW
散歩
Paseo
フアン・マルティネス=デ・ラス・リバス
Juan Martínez de las Rivas
Editorial Pre-Textos
『La casa limón(レモンハウス)』は、寓話に近い示唆的なトーンで、ルーマニアにおけるチャウシェスク政権の崩壊の年月を少女の無垢な目を通して描く。共産主義の終焉を生きる少女は、家族が直面する個人的な災難とトランシルヴァニア出身の祖父母が持つ古くからの伝統の間で、周囲で何が起こっているのかを理解しようとする。ダイニングテーブルの下に身を隠し、本の城に囲まれて、少女は、自分が期せずして父親の奇妙な病気を引き起こしてしまったのではないかと心配する。規制と悪名高いセクリターテへの密告が続く中、彼らは独裁政権の終焉が近づいていることを知らない。正確で、生々しいが夢のような筆致で描かれた、リリカルで感動的な小説。少女の声と全体主義の影が私たちに問いかける普遍的な物語。
詳しく見る

文学
NEW
レモンハウス
La casa limón
コリナ・オプロアエ
Corina Oproae
Tusquets Editores
すでに老境に入った二人の姉妹が、青春時代のお気に入りの映画を演じて遊ぶ。二人のティーンエイジャーが終業式の日に、これまでとは異なる視線で生々しく互いを発見する。ある女性が、彼女の人生を永遠に変えたパーティーを回想する。イタリアのある都市で、ひとりの男が大聖堂の建設現場に入り込み、予期せぬ結果をもたらす指令を受ける。巧みな心理描写と日常の微妙な混乱を用いて、説明不可能なもの、震撼とさせるもの、語られないもの、予期せぬ形で私たちを変え、決して忘れられなくなるものを浮き彫りにした短編集。
詳しく見る

文学
NEW
見えないもの
Lo que no se ve
クリスティーナ・フェルナンデス=クバス
Cristina Fernández Cubas
Casanovas & Lynch Literary Agency
プエブロ・チコは、時に霧に包まれ、雪に覆われる山間の小さな村だ。時に動物が迷い込み、人が姿を消すこともある山中にある。一見穏やかな場所で、今は数少ない寡黙な老人たちが住んでいる。その静けさに、秘密や暴力的な過去、復讐の念が隠れているとは、誰も思わない。1年間そこで過ごそうと都会からやってきた夫婦も何も疑っていない。しかし、父親がそこで生まれたという理由でそこに来ることを選んだアリアドナはやがて、山に何かが隠されていると感じ始める。村の住人たち、特に透き通るような目をして幻覚にも似た謎めいた言葉を話すペドロと出会い、アリアドナは父親が自身の過去についてなぜ何も語らなかったのかをようやく理解するようになる。それは、村全体が目を閉じ、見ないことにしようと決めた過去だった。 読者を巻き込むざらついた文体で書かれたこのポリフォニックな小説で、エドゥルネ・ポルテラはある村、ひいてはある国家、大陸、そして人類の集団的記憶を鋭く問いただす。
詳しく見る

文学
NEW
閉ざした目
Los ojos cerrados
エドゥルネ・ポルテラ
Edurne Portela
Galaxia Gutenberg SL
植物について何も知らない作家が、何年も手入れされずに放置されていた庭と家の世話を予期せずして引き受けることになる。引退間近の庭師が、彼に最初の手ほどきをする。その庭師が引退した後、作家はひとりで庭の手入れをし発見を続ける。本書は、庭を言葉で再現することを目的とする。生き物、植物、地元の人々との出会いの物語や、時の移ろいの観察を通して、いかにして彼が庭師となり、彼が手入れし創造する世界の断片がいかに生きていくかが綴られる。自然への研ぎ澄まされた視線を備えた文章は、訪れる人にその場所の秘密を教える散歩のようだ。
詳しく見る
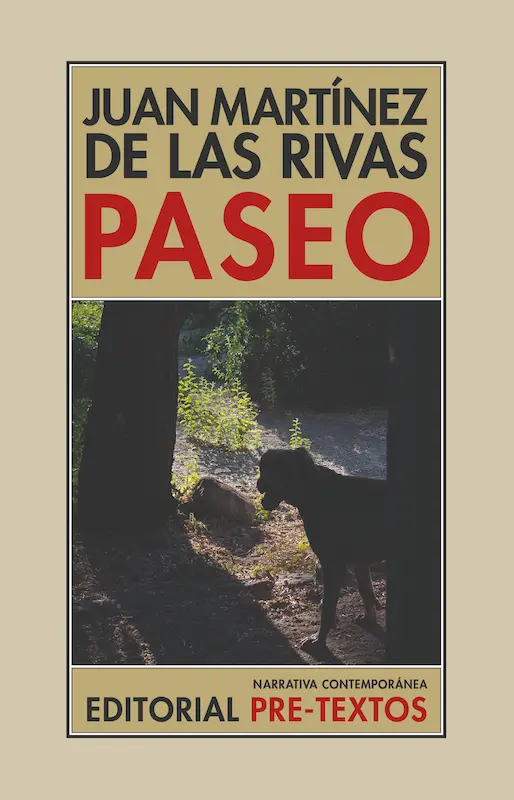
文学
NEW
散歩
Paseo
フアン・マルティネス=デ・ラス・リバス
Juan Martínez de las Rivas
Editorial Pre-Textos

文学
NEW
レモンハウス
La casa limón
コリナ・オプロアエ
Corina Oproae
Tusquets Editores

文学
NEW
見えないもの
Lo que no se ve
クリスティーナ・フェルナンデス=クバス
Cristina Fernández Cubas
Casanovas & Lynch Literary Agency

文学
NEW
閉ざした目
Los ojos cerrados
エドゥルネ・ポルテラ
Edurne Portela
Galaxia Gutenberg SL
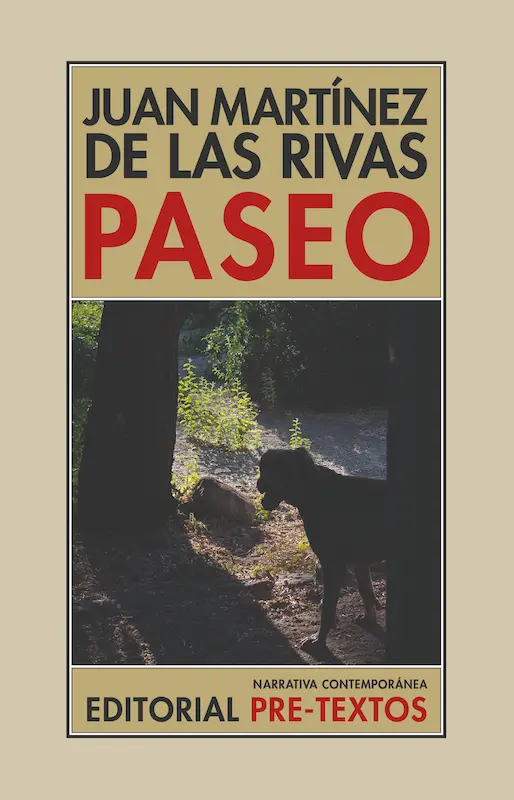
文学
NEW
散歩
Paseo
フアン・マルティネス=デ・ラス・リバス
Juan Martínez de las Rivas
Editorial Pre-Textos

文学
NEW
レモンハウス
La casa limón
コリナ・オプロアエ
Corina Oproae
Tusquets Editores

文学
NEW
見えないもの
Lo que no se ve
クリスティーナ・フェルナンデス=クバス
Cristina Fernández Cubas
Casanovas & Lynch Literary Agency

文学
NEW
閉ざした目
Los ojos cerrados
エドゥルネ・ポルテラ
Edurne Portela
Galaxia Gutenberg SL
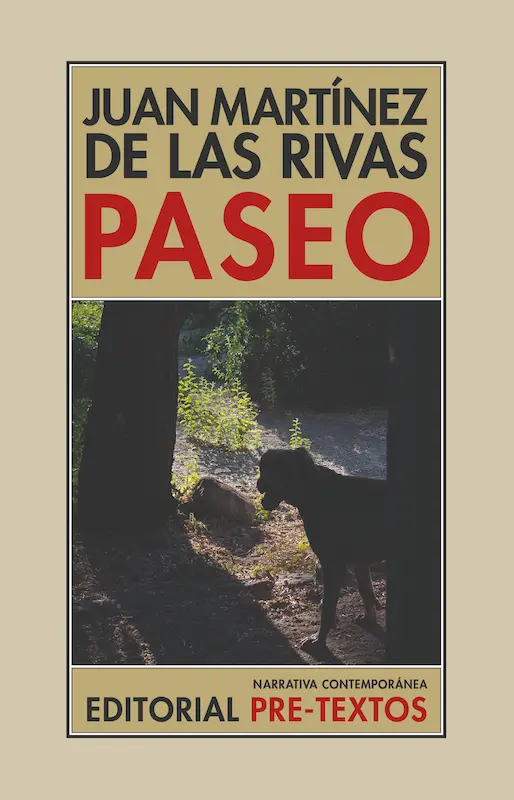
文学
NEW
散歩
Paseo
フアン・マルティネス=デ・ラス・リバス
Juan Martínez de las Rivas
Editorial Pre-Textos
絵本
私たちは皆、この世に生まれてきた瞬間からだれかを必要としています。生まれるためには母親が、成長するためには世話をしてくれる人が必要です…。この本は色鮮やかなコラージュと、「象に乗るには何人必要?」「寂しいと感じるには?」「キスをするには何人?」といった問いで満たされています。具体的な問題から抽象的な問いかけまで、ページの隅に隠された答えを見る前に、読者は自分なりの答えを見つけようと夢中になるでしょう。遊び心いっぱいに、アンナ・フォンは謎々をつなぎ合わせ、連帯のメッセージをちりばめます。それによって子どもは、「他者」が最大の贈り物であり、調和して暮らすためには互いに助け合うべきだと理解するでしょう。--セシリア・フリアス、エルムンド紙
詳しく見る

絵本
NEW
何人必要?
Quanta gent es necessita?
アンナ・フォン
Anna Font
Ute Körner Literary Agent, S.L.U.
読書への賛歌、いつまでも終わってほしくない本、常に私たちに寄り添ってくれる本へのオマージュ。そして子育てへの、一冊の本のように綴られていく人生へのオマージュ。いつまでも終わってほしくない瞬間、そして常に私たちに寄り添ってくれる瞬間へのまなざし。
詳しく見る

絵本
NEW
いつまでも
Que nunca se acabe
シモ・アバディア
Ximo Abadía
Litera Libros
私たちは皆、この世に生まれてきた瞬間からだれかを必要としています。生まれるためには母親が、成長するためには世話をしてくれる人が必要です…。この本は色鮮やかなコラージュと、「象に乗るには何人必要?」「寂しいと感じるには?」「キスをするには何人?」といった問いで満たされています。具体的な問題から抽象的な問いかけまで、ページの隅に隠された答えを見る前に、読者は自分なりの答えを見つけようと夢中になるでしょう。遊び心いっぱいに、アンナ・フォンは謎々をつなぎ合わせ、連帯のメッセージをちりばめます。それによって子どもは、「他者」が最大の贈り物であり、調和して暮らすためには互いに助け合うべきだと理解するでしょう。--セシリア・フリアス、エルムンド紙
詳しく見る

絵本
NEW
何人必要?
Quanta gent es necessita?
アンナ・フォン
Anna Font
Ute Körner Literary Agent, S.L.U.
読書への賛歌、いつまでも終わってほしくない本、常に私たちに寄り添ってくれる本へのオマージュ。そして子育てへの、一冊の本のように綴られていく人生へのオマージュ。いつまでも終わってほしくない瞬間、そして常に私たちに寄り添ってくれる瞬間へのまなざし。
詳しく見る

絵本
NEW
いつまでも
Que nunca se acabe
シモ・アバディア
Ximo Abadía
Litera Libros
コミック
糖尿病に関する初の自伝的コミック作品。マリナは糖尿病と診断されたとき、すべてはこれまで通りだと思った。でもそこからは、何もかもが以前と同じではなくなる。毎日、生き続けることを心配しなければならない少女のリアルな生活とは? マリナ・テナは若い世代の読者に向けて、幼少期から大人になるまでの、自身の糖尿病についての経験を正直かつ感情豊かに描く。それらは、慢性疾患と診断された他の多くの少年少女の経験でもありうる。大切なのは病気だけでなく、人生への愛情、日々の些細なことへの情熱、そして何よりも人としての成長であるという、力強い人生の手引書。
詳しく見る

コミック
NEW
甘い
Dulce
マリナ・テナ
Marina Tena
MARINA Books
犬の色の見方は私たちと異なり、世界の捉え方も違っている。彼らの視線はより強く、共感的で、寛大だ。黒いラブラドール犬、トルファの目を通して、働き者だが感情的には淡白な父親、ホセ・ルイスの家族の日常が描かれる。愛するということの様々な形を描いた物語であり、老いた夫婦、病気の母親、そして冷淡な父親の沈黙を破ろうとする娘という、繊細な家族の記録でもある。
詳しく見る

コミック
NEW
トルファ
Trufa
グラフィラ・スミス
Glàfira Smith
Brink Books
糖尿病に関する初の自伝的コミック作品。マリナは糖尿病と診断されたとき、すべてはこれまで通りだと思った。でもそこからは、何もかもが以前と同じではなくなる。毎日、生き続けることを心配しなければならない少女のリアルな生活とは? マリナ・テナは若い世代の読者に向けて、幼少期から大人になるまでの、自身の糖尿病についての経験を正直かつ感情豊かに描く。それらは、慢性疾患と診断された他の多くの少年少女の経験でもありうる。大切なのは病気だけでなく、人生への愛情、日々の些細なことへの情熱、そして何よりも人としての成長であるという、力強い人生の手引書。
詳しく見る

コミック
NEW
甘い
Dulce
マリナ・テナ
Marina Tena
MARINA Books
犬の色の見方は私たちと異なり、世界の捉え方も違っている。彼らの視線はより強く、共感的で、寛大だ。黒いラブラドール犬、トルファの目を通して、働き者だが感情的には淡白な父親、ホセ・ルイスの家族の日常が描かれる。愛するということの様々な形を描いた物語であり、老いた夫婦、病気の母親、そして冷淡な父親の沈黙を破ろうとする娘という、繊細な家族の記録でもある。
詳しく見る

コミック
NEW



